1.ウクライナ支援は“正しい”のか?
日本はウクライナに対し、これまでに1兆8000億円の支援を続けてきた。
これは「人道支援」や「正義の行為」として、国内でも大きく報じられ、疑われることも少ない。
だが、同じように制裁・封鎖・戦時的状況にある国、イランに対しては、日本は支援をほとんど行っていない。
「なぜ日本はウクライナには支援し、イランにはしないのか?」
その”当然とされた区別”の中に、わたしたちは思考的バイアスを見落としてはいないだろうか?
2.背景:ウクライナとイラン──両国の状況比較
これは感情論ではない。
どちらも困っている国であり、どちらも人道的課題を抱えている。
それにもかかわらず、支援の「有無」には明確な差が存在している。
| 視点 | ウクライナ | イラン |
|---|---|---|
| 支援額(日本) | 約1兆8000億円 | ほぼゼロ |
| 国際的ポジション | 欧米寄りの“正義陣営” | 制裁対象、敵対視されがち |
| 被害の語られ方 | 市民の苦難、支援の必要性 | 核・宗教・武装・報復 |
| 共感される要素 | 明示的(避難民・戦火) | あいまい、または隠されがち |
| 内部状況 | 汚職・中抜きの懸念あり | 国家機能は維持されている |
一部の報道では、ウクライナの支援金のうち最大50%が中抜きされているとの指摘もある。
一方、イランは経済制裁により苦境にありながら、国家基盤や医療制度を維持している。
3.かつての日本とイラン──信頼と石油の記憶
イランは日本にとって“遠い国”なのだろうか?
実は日本とイランは、かつて極めて良好な関係にあった。
- 日本は長年、イランから安定的に原油を輸入してきた。
特に1970〜2000年代前半までは、イランは主要なエネルギー供給国の一つだった。 - イラン革命後も、日本はアメリカとは一線を画し、外交ルートを保持し続けた。
- 2011年には大地震の際、イランからの支援も送られている。
この関係が壊れたのは、「イランが危険になったから」ではない。
アメリカ主導の制裁によって、“そう見なされるようになった”からだである。
ここで見えてくるのは、「関係の冷却が必然ではなく、制裁による副作用である」ということだ。
日本とイランとの間には、かつて確かな信頼があった。
にもかかわらず、いま日本は「イランに支援できない構造」に囚われている。
4.イランは支援を受けづらい構造的障壁がある
「イランは危険だから支援できない」
「イランはテロ国家だから当然」
そういった声はしばしば聞かれる。
ここで表面化するのは、日本の支援行動が「西側=善」であり、その「敵対国=悪」という思想に組み込まれている事実だ。
(※西側とは、アメリカを中心とした資本主義の国々のこと)
その背景には、支援を受けにくくなる制度・情報・思想の三重障壁構造が存在している。
- 経済:経済制裁により、国連・NATOの枠組みを通じた物流・資金流通が制限
- 思想:イラン=反米・独裁・テロという固定観念が根付いている
- 情報:ウクライナが「支援されるべき国」として語られる一方で、イランは「危険で敵対的な国」と語られる
そもそも、“支援していい国”の定義は、誰がどこで決めているのか?
5. 日本の立場:なぜイラン支援こそ“独立外交”の第一歩なのか
ウクライナ支援は、アメリカや欧州と日本の同盟関係に基づいて行われている。
しかしそれは、日本が「誰の基準で動いているのか?」という考えを避けたものでもある。
- イランは中東の大国であり、日本のエネルギー外交のキープレイヤーでもあった。
- 人道的災害・制裁下での困窮も確実に存在する。
今支援しないことは、中立ではなく“黙認”という加担ではないのか?
ここに手を差し伸べることこそが、「日本独自の支援」を世界に示す一歩になり得る。
6.「感情で選ぶ支援」ではなく「戦略で選ぶ支援」へ
「かわいそうだから支援する」
「報道されてるから支援する」
それは、支援の“中身”ではなく“見え方”で決めていないだろうか?
一方で、イランに対してどうか?
- 共感が成立しづらい
- 批判リスクもある
- アメリカの顔色があり、支援の正当化がしづらい
ゆえに「支援しない」が“無難”とされる。
だが、それは戦略ではなく、忖度と慣性でしかない。
7.「誰かの正義に乗るのではなく、“意図ある支援”が日本を変える」
支援とは、「可哀そうだから」で助けるのではない。
支援とは、正義の演出ではない。
支援とは、未来との関係を選び取る行為そのものだ。
その選択の手綱を、他国の論理に委ねるべきではない。
制裁の網をすり抜けてでも、日本が選び取れる“意図ある支援”を届ける方法はある。
たとえば:
- 医療・教育・農業・災害復興による非軍事的・文化的支援
- NGO・赤新月社などを通じた間接的支援の活用
「なぜ我々は“支援しないこと”に慣れてしまったのか?」
ウクライナ支援が「称賛される行為」であるなら、イラン支援が危険視されるのだとしたら、
そこには“支援そのもの”に政治的なバイアスが組み込まれているということだ。
支援する自由があるなら、
支援しないことを問い直す自由もまた、持つべきではないか。

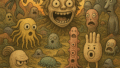
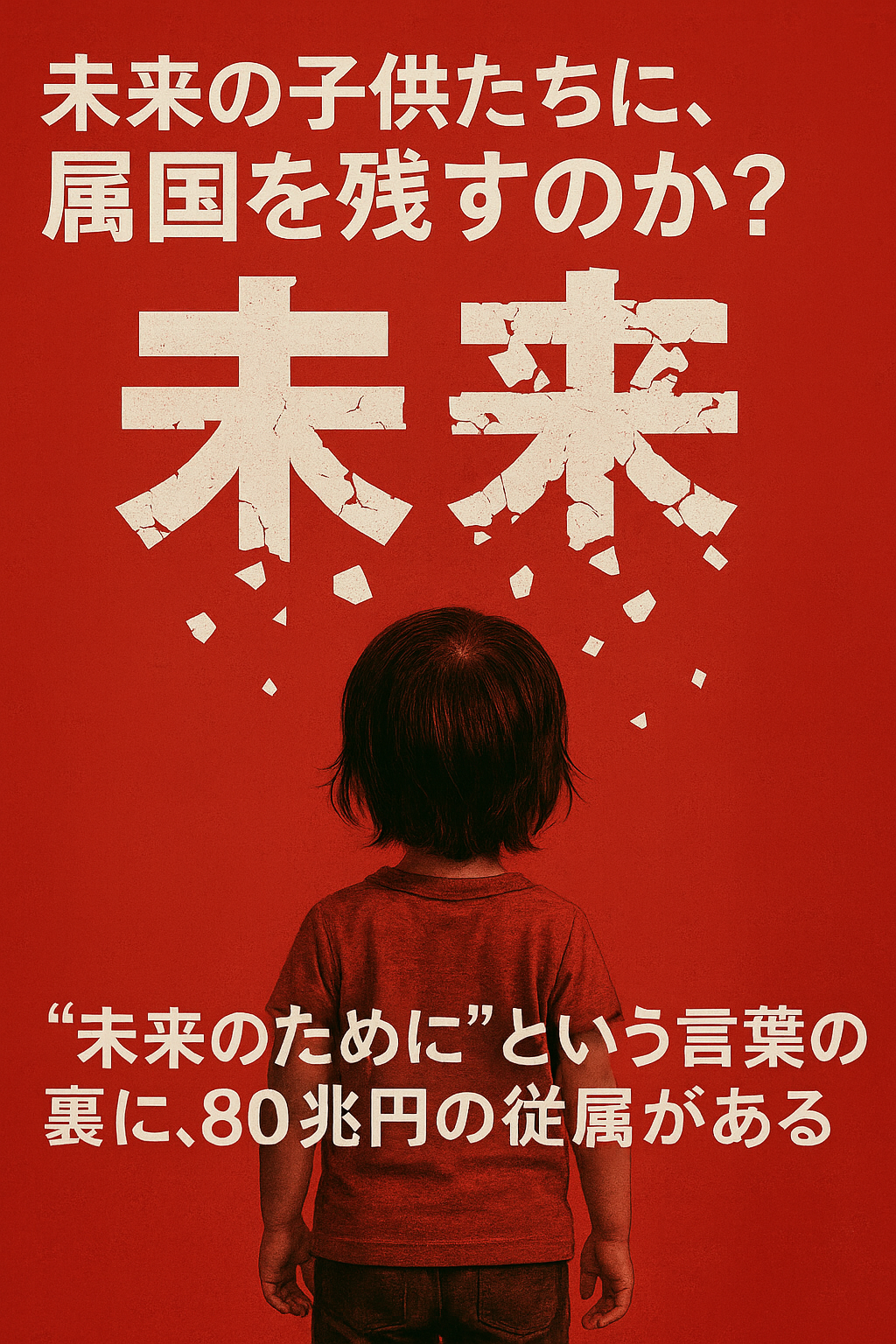
コメント