2024年12月、自民・公明・国民民主の3党間で交わされた合意文書に、こう書かれていた。
「ガソリン税の旧暫定税率は廃止する」
与党側が明記した“約束”は、物価高騰に苦しむ国民にとって一筋の光だった。
政治の対立ではなく、生活に対する対応としての減税──その流れは、ようやく本格化するかに思えた。
だが、2025年6月。
法案が衆院で可決されると、自民党は参院で採決すら許さなかった。
政金融委員会の自民党・三宅伸吾委員長は委員会を採決をせずに閉会し、合意は無視された。
あの合意は何だったのか?
これは民主主義なのか?
それとも、政治における「約束」は、守る気がなければ無価値なのか?
第1章:制度が形式を守って“民意”を封殺した
1.3党合意で見えた希望
ガソリン税の「旧暫定税率」は、かつて道路特定財源として導入された暫定措置だった。
だが、制度はその後も恒久化され、名ばかりの“暫定”がいまも続いている。
2024年12月、自民・公明・国民民主の与党系三党は、この旧暫定税率を廃止する方針で合意した。
政府与党の幹事長同士が取り交わした合意文書には、「暫定税率の廃止」の文言が明記された。
国民の側に立てば、この合意は「生活に根ざした減税の兆し」として大きな期待を生んだ。
2.衆院可決と参院ブロック
2025年6月、野党7党が「旧暫定税率の廃止法案」を衆議院に共同提出。
内容は簡潔で、7月1日から旧暫定税率を廃止するという明快なものだった。
この法案は、与党が過半数割れとなった衆議院を通過し、可決された。
形式上は、合意を実行に移すチャンスが整ったように見えた。
ところが、参議院では事態が急変した。
審議は一度開かれたものの、法案の採決には至らなかった。
財政金融委員会の自民党・三宅伸吾委員長は、審議の途中で「休憩」を宣言し、そのまま再開することなく閉会したのである。
さらに、法案を次の会期に引き継ぐための「継続審査」の手続きも取られなかった。
その結果、会期末での自然廃案──制度上のルールに基づき、法案は静かに消滅した。
手続きは踏まれた。しかし、その中身は、「審議の場そのものを物理的に消す」という政治的判断だった。
議論は止まり、採決は行われず、記録にも残らない。
そして、国民が注視した“約束”は、うやむやのまま歴史の帳簿から消された。
3.形式を守って実質を潰す
形式的には、ルール違反はない。
参議院では与党が多数を占めており、議運や委員会の運営をコントロールする権限も正当に持っている。
だが、民主主義とは単に手続きが守られていればそれでよいのか?
議会制民主主義の根本は、「賛成」「反対」いずれであれ、国民の声が議論という形で反映されることにある。
今回、自民党は「反対」すらしなかった。
反対と表明することさえ避け、記録にも残させず、静かに“無かったこと”にした。
このような「審議をさせない」という封殺の手法は、民主主義の手続きを装った、構造的な意思の拒絶である。
そしてその拒絶は、国民に対して明確なメッセージを返した──
「あなたの生活より、わたしたちの都合のほうが優先される」と。
第2章:「多数派=正義」という幻想
日本の議会制民主主義は、多数決によって物事を決める仕組みで成り立っている。
国民が投票によって選んだ政治家が議席を得て、多数派が政策を決定する──それは一見、公平で透明なルールに思える。
1.多数決は民意を反映しているのか?
今回のガソリン税法案の経緯が示したのは、「多数派」が必ずしも民意を反映しているとは限らないという厳然たる事実だった。
参議院で自民・公明が多数を持つ限り、どんな法案でも審議の途中で止めて、採決に至らせずに握り潰すことが制度上可能である。
与党にとって不都合な議論は、「審議を止める」という選択肢によって、黙殺されうる。
今回のガソリン税廃止法案は、衆議院での可決を経たにもかかわらず、参議院では採決すらされなかった。
そして「採決に至らなかったものは、記録にも残らない」。
2.審議を拒むという支配の形式
ここで起きているのは、多数決ではなく、“議論の起動と停止を制御する力”の独占である。
「反対」すら言わないことで、政治家たちは自らの責任を回避し、民意との対話を一切断ち切るという選択をしている。
こうした振る舞いは、もはや「民主主義の原理」ではなく、“選ばれた者による統治”──
つまり、手続きを通じた静かな独裁と呼んでも過言ではない。
3.形式的正当性の罠
制度上の正当性は保たれている。
「選挙で選ばれた与党が、委員会運営の裁量権を行使した」──この説明に異を唱えることは難しい。
しかし、それはあくまで形式的な正当性にすぎない。
多数派の背後にある民意が、時に少数派や無視された声を踏みにじっていないか?
賛否の記録すら残らない沈黙の中で、誰が「決定」を下しているのか?
4.民主主義は「数」ではなく「誠実な議論」
「選ばれたから正しい」のではない。
正しさとは、選ばれた者が誠実に議論の場に立つことで初めて証明されるのではないか。
民主主義の価値とは、数の力ではなく、声と声が交わる場を開くことにある。
今、私たちはそれを失いつつある。
第3章:なぜ“採決拒否”という手法が許されてしまうのか?
1.責任を伴わない「審議拒否」
法案を通さない方法には、大きく2つある。
一つは「反対して否決する」こと。もう一つは「採決すらさせない」ことだ。
前者には責任が伴う。反対したという記録が残り、批判も受ける。
一方、後者には責任が伴わない。記録されず、発言すらしていないのだから、説明も必要ない。
今回、自民党が選んだのは後者だった。
ガソリン税の廃止に反対する意思を明言することなく、議論のステージそのものを閉じることで“表向きの中立”を演出した。
2.「異例」と報じられても止まらない
今回は、ニュースでも「異例の土曜審議」として報じられ、SNSでも話題になった。
かつてなら見逃されたかもしれない動きが、今は多くの目に晒されている。
それでも、「採決拒否」は実行された。
ここに、かえってこの戦術の“強さ”が表れている。
たとえ注目を浴びても、明確な反対を表明しなければ、「責任」は発生しない。
声を上げた側が“感情的”や“極端”と見なされ、一方で沈黙を貫いた側は「冷静」「穏健」の立場に見える。
3.“沈黙”の力を使いこなす政治家たち
政治家たちは、国民の無関心だけでなく、「関心の持続性」にも精通している。
数日の報道とSNSの盛り上がりをやり過ごせば、やがて世論は次の話題へと移っていく。
特に選挙が近い時期には、敵を作らず、記録を残さず、ただ“スルーする”ことがもっとも損の少ない選択肢となる。
つまり、「なかったことにする」ための沈黙戦術は、政治的リスクを最小化する洗練されたスキルとして機能しているのだ。
4.パフォーマンスの中でも「立った者」と「逃げた者」
今回、野党は「7月からのガソリン税暫定税率の廃止」を求める法案を提出し、
明確にその是非を問う姿勢を示した。
それは、成立可能性が低いとわかっていても、「反対の立場に立つ」という政治的責任を取る行為だった。さらに、自民党・三宅委員長の対応に対して解任決議案を提出するなど、記録に残る行動も取っている。
もちろん、こうした動きにもパフォーマンス的な側面はあるだろう。
だが、それでも彼らは議論の場に立ち、記録に責任を刻んだ。
その点で、民主主義の最低限のルール──対話と応答の責任を果たそうとしたと評価できる。
一方、与党は法案に対して賛否すら示さず、「議論そのものを成立させない」という選択をとった。
これは、“賛否を記録させない”という沈黙の戦術である。
「立った者」と「逃げた者」──この違いは、結果ではなく姿勢に現れる。
それは、制度の中における誠実さの有無として、歴然とした対比となって現れている。
5.制度が許す「沈黙の統治」
「沈黙によって全てを回避する」制度が許されている限り、民主主義は少しずつ、対話のない支配体制へとスライドしていく。
それは、民意の表出が構造的にブロックされることを意味する。
そしてその独裁的手法を許してきた、私たち国民自身にも問題があるのではないだろうか。
第4章:形式の中で失われた“声”──民主主義の自壊
日本の政治制度は、憲法に基づき、選挙で選ばれた議員によって構成される議会が、定められた手続きのもとで政策を決定するという建前を持っている。
ガソリン税法案をめぐる今回の一連の流れも、外形的にはそのルールに則って処理された。
だが──形式が守られていたからこそ、かえって見えづらくなった“破壊”があった。
1.手続きの中で何が失われたか
問題は「違法行為」ではない。
むしろ、すべてが合法の手続きの中で、民意が通る通路そのものが意図的に封鎖されたということにある。
ガソリン税の減税という、生活に直結する政策について、
「議論が起きる場」「賛否が問われる場」「記録に残される場」──そのすべてが排除された。
国会で採決されなかった以上、反対の理由も記録されず、議事録にも残らない。
制度の枠内で沈黙することが、最も効果的な拒否手段として機能してしまった。
2.議論が記録されないという損失
民主主義の本質とは、多数決で物事を決めることではない。
むしろ、「異なる声を記録し続けること」にこそ、民主主義の意義がある。
今回、野党が提出した法案は、審議すらされずに廃案になった。
それに反対した与党の姿勢は、記録にすら残っていない。
声が立ち上がり、制度の中に届こうとした瞬間、それは沈黙という形式で圧殺された。
そして、記録に残らなかったものは、なかったことになる。
3.制度を使った“静かな統治”
議論を拒むことが可能な制度。
反対を表明せず、説明も不要なまま、民意を回避できる構造。
それは、形式に則った統治のように見えて、誠実な対話を根底から破壊する「静かな独裁」に他ならない。
この構造では、「声をあげなかった者」が責任を問われることはない。
むしろ、「声をあげようとした者」が制度に黙殺され、何もなかったことにされる。
4.記録されなかった声は、殺される
制度によって言葉が封じられるとき、それは暴力による支配と本質的に変わらない。
選挙で選ばれた者が沈黙を選び、採決という場を閉じたとき──
そこにいたはずの民意は、「存在しなかったこと」になっていく。
言葉が殺され、記録から消えるとき、民主主義の“死”は静かに進行する。
歴史を見れば、法の形式を守りながら人を裁いた政体はいくらでもあった。
そこでは「身体」が処刑されたが、今この国で進んでいるのは、制度によって“言葉”が殺される構造的な私刑である。
民主主義とは、「声を上げる自由」が保障されるだけではなく、
その声が制度の中で“記録”され、“議論”され、“反映される可能性”を持つことで初めて成立する。
今、私たちは──その最低限の回路すら、合法的に閉じられる現実を、目の前にしている。
最後に
ガソリン税の“旧暫定税率”は、かつて「暫定的」と呼ばれながら、いまなお制度として残り続けている。
だが、それは単なる税制の問題ではない。
政治が生活と向き合うことを、いつのまにかやめてしまった証である。
提案された法案が、議論もされず、採決もされず、
ただ沈黙の中で、制度に吸い込まれていく──その過程で失われたのは、
声であり、期待であり、記録であり、そして未来の判断材料だった。
1.「合意」は守られず、「責任」は空白のまま残された
今回の法案は、過去の政府が交わした“合意”に基づいて提出されたものであり、
国民が選挙で託した代表たちが、責任を持って向き合うべき対象だった。
だが、採決すらされずに廃案となったこの結果に対して、
「それでもルールは守られていた」と語る政治家がいるなら、そのルールが誰のためのものだったのか、改めて問う必要がある。
議論を避けることが、責任を回避する手段になっている。
そこに「政治の誠実さ」は、もはや存在しない。
2.民主主義とは、語り合うことを前提にした構造のこと
民主主義とは、選挙で終わるものではない。
語り合い、異なる声を可視化し、記録に残していくことが、その核心にある。
議論を避け、形式で蓋をし、沈黙によってすべてを処理する現在の構造は、
もはや「民主主義を模した統治」にすぎないのではないか。
語られない政治は、やがて語る力そのものを社会から奪う。
そして、それに気づかないまま日々を過ごす私たちは、知らぬ間に「声を失うこと」に慣れていく。
3.そして、わたしは問いを投げる
与党によって審議入りを拒否された法案は、採決すらされず、誰が何を主張したかの記録も残らない。
反対も賛成も「なかったこと」にされるその過程で、私たちの声は、議事録の片隅にすら残らない。
そうして、未来の誰かが過去を振り返ろうとしたとき、何も“議論の痕跡”が見つからない社会が出来上がる。
だから私は問いたい―――
「議論を拒否する政治を、民主主義と呼んでいいのか?」
と。
これは政治家だけへの問いではない。
この社会に暮らす、私たち一人ひとりへの問いでもある。
合意が破られ、議論が閉じられ、声が届かなくなったこの制度の中で──
もう一度、「語り合う民主主義」という原点を思い出すきっかけになることを願って。


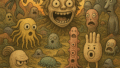
コメント