2025年4月2日、ドナルド・トランプ大統領はホワイトハウスで演説を行い、貿易相手国の関税状況を踏まえた「相互関税」の導入を発表した。
内容は実に単純で、すべての輸入品に一律10%の関税を課し、中国には34%、日本には24%といった国別の追加関税を設定するものだった。
各メディアから様々な意見が出た。
「計算式に誤りがある」「一貫性がない」と、批判の声は多く株価は急落。市場も混乱した。
だがここで一度立ち止まって考えてみたい。
本当に、米国の貿易赤字解消を目的に進める政策が本質なのだろうか?
本当にこの政策は、“数字を揃える”ための手段なのだろうか?
それとも、「敵と味方を線引きする」ための選別だったのではないか。
トランプ大統領にとって、この関税政策は「結果」を目指す政策ではなく、「実行すること自体」が目的だったのではないか?そう考えると、この一連の動きが少し違った意味を持ち始める。
従来から言われているトランプ大統領のポピュリズム、「敵か味方か」を塗り分ける”踏み絵”としての政治構造としての一面で考えていきたい。
踏み絵の原型はすでにあった
ゼレンスキーとの会談に見えた主従構造
相互関税の発表が世界を揺るがす前、2025年2月28日、ホワイトハウスではすでに“第一の踏み絵”が始まっていた。
ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカの支援継続をめぐり、トランプ大統領と会談の場を持った。そのやりとりは、外交とは呼べないほど感情的だった。
「君は“ありがとう”を言ったか?」
「カード(交渉材料)はないだろう?」
「我々がいなければ2週間で終わっていた」
「態度を変えろ」
これは、協調や理解を目的とした会談ではなかった。
支援の見返りに“忠誠”と“感謝”を要求する、いわば主従確認だった。
ゼレンスキーは国際社会で独立を保ち、戦争を耐え抜いてきた国家の代表として、トランプは世界最強の軍事と資金を握る支配者として対峙していた。
そしてこのやりとりは、「踏み絵」という構造の縮図だったとも言える。
「我々の支援が欲しければ、我々に従順であれ」
この発想こそが、後に相互関税という名の政策に形を変えて現れる。
経済政策に見えるが、その根底には“敵味方を選別するロジック”がすでに内在していたのだ。
ゼレンスキーに対する問いは、「感謝したか?」という単純な言葉でありながら、その実、「誰の側に立つのか」を試すための踏み絵だった。
この“踏み絵”の論理は、何も外交に始まったわけではない。
トランプという政治家そのものが、「敵か味方か」を明確に線引きし、選別することで勢力を固めてきた存在だ。支持者に向けた選挙戦から、メディアとの対立、政敵へのラベリング。
すべてにこの構造が貫かれている。
そしてその論理は、外交で試され、今度は経済の場へと持ち込まれた。
止まらなかった関税政策を止めたのは、“市場”だった
米国債売却がもたらしたトランプの方向転換
2025年4月2日、ドナルド・トランプ大統領は“相互関税”を発表。
全輸入品に一律10%、加えて中国製品には34%、日本には24%、その他国ごとに異なる追加関税を課すという前代未聞の関税政策だった。
発表を受け、世界のマーケットは大きく揺れ、ダウ平均は1,300ポイント超の下落を記録した。
株価が落ちようが、批判が出ようが、“踏み絵”は続行された。
だが、数日後、状況は急転する。
機関投資家が米国債を売却したのだ。
その影響で、米国債の利回りは急上昇。価格は急落。
アメリカ政府にとっては、“信用の証文”が傷ついたに等しい事態だった。
トランプは突然、「相互関税の追加分を90日間停止する」と発表した。
この一連の流れを、時系列で整理するとトランプ政権の反応パターンが浮き彫りになる。
| タイミング | イベント | 分類 | トランプの反応 |
|---|---|---|---|
| 4月2日 | 相互関税の発表 (全輸入品10%、中国34%、その他国別) | 政治的攻勢(踏み絵) ポピュリズム演出 | 発表強行。 「アメリカ第一」を強調。 |
| 同期間 | ダウ平均1,300ポイント超の暴落 | 株価(リスク資産への打撃) | 耐える姿勢。方針変更なし。 |
| 同期間 | ドル安進行 | 通貨価値への揺らぎ | 無視。 |
| 4月9日 | 機関投資家の米国債売却 | 債券安(国債価格暴落) 金利急騰 → 米財政へのダメージ | ここで態度急変。 方針を“90日停止”に修正 |
| 4月9日 | 「報復しなかった国には関税を停止」 「中国には145%課税」 | 政治的撤退×一部強硬 | 「市場がパニックだった」 とトランプ自ら認める |
「報復しなかった国には猶予を与える」そう語ったトランプだったが、その前日まで一切そんなそぶりは見せていなかった。
「市場が混乱していた。だから判断を変えた」とトランプ大統領が明言したように、株安やメディア批判ではなく、“債券安”が彼の判断を変えたのだ。
株安は耐えた。だが、“国債”にはひるんだ
ここで見えてくるのは、トランプの“限界点”がどこにあるのかということだ。
| ショックの種類 | トランプの対応 |
|---|---|
| 株安(ダウ1,300pt) | 無視/強行継続 |
| ドル安 | 容認/輸出には有利と主張 |
| 債券安(米国債売却) | 即座に方向転換(関税停止) |
トランプが関税を武器に踏み絵を迫るなか、“市場”が踏み返してきたのは、まさにこの瞬間だった。
トランプはなぜ中国には145%を課したのか
トランプ大統領は中国からの報復関税を受け従来の34%から145%へと引き上げた。
これは、追加分という次元を超えた、制裁的な関税である。
ここまでくると、もはや貿易停止である。
なぜ中国だけが“桁違い”の制裁対象なのか
表面的な理由としては、「中国からの報復があったから」。
だが、本質的にはもっと構造的な問題がある。
- 製造業の脱中国を促進したい
→ 米企業にとって中国は最大の生産拠点。だが、それは“依存”でもある。
→ 高関税を課すことで、「もう中国で作るのは損」と思わせる圧力をかけている。 - 地政学的対立を経済戦に持ち込んでいる
→ 台湾問題・南シナ海・ハイテク規制…すべてが経済と安全保障に絡む
→ 経済的な“切り離し”を関税で強引に進めている - 内政向けの敵イメージ
→ 中国を叩くことは、支持層(ラストベルトや白人保守層)への“わかりやすいアピール”
→ 「敵がいる」「戦っている」ことで、政治的な求心力を維持する
中国経済は“盤石”なのか?
中国はこの制裁に耐えうる体力があるのか?という点だ。
中国は「世界2位の経済大国」であり、「世界の工場」であり、「人民元も強くなった」。
だが、その内部は決して無傷ではない。
「ゾンビ銀行」化の進行
不動産バブルの崩壊により、地方政府や大手開発企業が連鎖的に資金ショート。
国有銀行はそれらを支えるため、利息の支払われない融資を大量に抱えるようになった。
だが、貸倒れ処理はされず、政府の“支え”で見かけ上の安定を保っている。
政府のヤバい薬を注入され、本来であれば信用の上に成り立つ金融がゾンビ銀行化しているのだ。
「破綻はしていないが、生きているとも言えない」
→ 信用の上に成り立つ金融が、“虚構の安定”で回されている。
とは言え、第一次トランプ政権後より、中国はこの構造的な苦境に対して対抗軸の構築も進めている。
ASEAN・中東・アフリカなどと連携し、自前の経済圏(脱アメリカ圏)を模索中であり、
一部では元建て取引の拡大や、人民元通貨圏構想にも現実味が帯びつつある。
また、ハイテク分野においても最新技術やEV・半導体など特定領域での自立を進め、全体ではなく“部分的勝利の積み重ね”を戦略の柱としている。
アメリカが“選別する側”であるなら、中国は“新たな秩序を名乗る側”として動き始めている。
そして、世界はその狭間で新しい分断を受け入れざるを得なくなってきている。
経済はもはや、選別の道具である
経済政策とは、成長や安定のためにあると思われていた。
だが、トランプ大統領が掲げた”相互関税”は、その常識を覆した。
関税は、結果ではなくメッセージ。
支援は、取引ではなく忠誠心の確認。
混乱は、失策ではなく選別の道具。
トランプ大統領が求めているのは、協調ではなく従属であり、共存ではなく選別だ。
では、選別された先には何があるのか。
中国は、経済圏の再編へと舵を切った。
アメリカがその代償を支払わずに済むのか──
それを決めるのは、通貨でも関税でもない。“選ばれる側の論理”かもしれない。

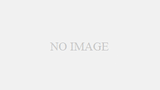
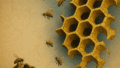
コメント