最近、夢を見た。それはひどい夢だったように思える。
単調な音楽、単調な漫画、安全安心へと振れた創作ばかりの未来。
かつて、ヲタク文化・ヲタク大国と呼ばれた日本が目指したものはそれだったのだろうか?
SNSを開けば生成AIを使った絵、漫画、動画ばかりが流れてくる。
10年どころか、2,3年前では考えられなかったことだ。
今まで人的リソースに依存していた産業が、AI生成コンテンツに圧倒されていることを示している。もはや生成AIを使った作品は大量に市場に流通し、人間作家の創作速度では太刀打ちできない状況になっているのだ。
一方で、生成物が著作権や性的表現規制に触れるケースも多く思える。
AIは低コストで高速という特徴を持ち、これまで専門的な技能や知識のジャンルに容易に参入できるようになった。
今後はこれが加速度的に増え、エロ漫画や同人誌、果てには実写ポルノといった嗜好性産業を圧巻するだろう。
かつて商業的に成立しなかった少数派フェチズムが再び流通することになるのだ。
一見するとこれは「多様性の復活」が起きたように思える。
果たしてそうだろうか?
生成AIの拡大は、やがて社会的反発を招くことになる。今ですらそうだ。
著作権侵害、ディープフェイク、性的暴力的内容の拡散…etc
これらの課題によって、行政やプラットフォームなどが規制路線へと介入を始めることだろう。
その結果、多くの国や企業が「AI生成コンテンツ」全体に対して制限し、特に性的表現領域では、「AI=潜在的リスク」となり、自主規制が高まる。
これはプラットフォーム側だけではない。生成AI自体のアルゴリズムにもメスが入るだろう。
このとき、AIに完全依存していたジャンル、ニッチな嗜好や成人向けは大打撃を受ける。
AIが文化を破壊するのだ。
焼け野原と化した文化は、もはや復元不可能となる。
AIによって解放されたジャンルだったにも関わらず、規制によって二度と戻らない空白地帯となる。
今、現状のSNSに流れてくる情報を思い浮かべてほしい。
他にも同様のことになるものが浮かばないだろうか?
先に言った漫画、イラストはもちろんのこと実写ポルノ、音楽、詩、なんなら児童向けの絵本すらも対象になりそうに思える。
共通点は非効率で非倫理だろう。
AIと規制の両方が「扱いづらい」と感じるものほど社会的に消えていく。
生成AIの普及は、創作を広げたように見えて、実際は倫理規制と文化的淘汰につながる。
AIが門を開き、社会がそれを危険とし、結果として誰も入れなくなる。
この連鎖は創作の多様性を脅かす最大のリスクだ。
AI時代の問題は「AIが仕事を奪うこと」ではない。
AIと規制の相互作用によって、誰も表現できなくなり、伝統工芸と化すことなのだ。
AIは創作を加速させると同時に、倫理や制度の摩擦によって文化の断絶を生むことになる。
さまざまな表現が、AI化と規制を経て一斉に消えることになるだろう。
それは、数年後、10年後になるかは分からない。
人間の創作が存続するかどうかは「効率」ではなく「何を残したいか」をにかかっている。


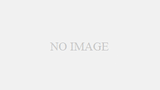
コメント