2025年9月、「一般社団法人ワクチン問題研究会」が厚生労働省に対してmRNAワクチンの承認取消と市場回収を求める意見書を提出し、記者会見を行った。
新型コロナが国内初の感染者が確認されて約5年。ワクチンが導入され4年以上が経過した今、このような要望が公的な場で出されるのは異例である。
過去の薬害事件を想起させるようなフレーズが飛び交う一方、厚労省や主要学会は「現時点では承認を維持する」との立場を崩していない。
では、この要望を出した団体はどのような組織なのか。そして、薬害の歴史と今回の公衆衛生対応は本当に同列に語れるのか。
1.一般社団法人ワクチン問題研究会とは
一般社団法人ワクチン問題研究会は、2023年に設立された民間団体である。
代表は京都大学名誉教授の福島雅典氏で、理事には地域の開業医や研究者が名を連ねる。主な活動は、mRNAワクチン接種後に長期的な症状を訴える「ワクチン接種後症候群(PVS)」の調査や救済要望、政策提言だ。
ただし、日本医学会連合や主要学会に属する公的な学術団体ではなく、弱者擁護的な色合いの強い専門家ネットワークと位置づけられる。英文論文の発信も行っているが、掲載誌は査読の堅牢性や評価に議論があり、主流学術界で広く受け入れられているとは言い難い。
こうした背景から、同団体の主張が政策判断に直接反映されにくい理由は、以下の四点に整理できる。
| 観点 | ワクチン問題研究会の立場・発信 | 主流学術・公的評価の状況 | 受容が広がりにくい要因 |
|---|---|---|---|
| 発信先(論文掲載誌) | 「Science, Public Health Policy & the Law」に英文論文を掲載 | PubMed/MEDLINE未収載、大手出版社系列ではない | 規制当局や大手学会が参照する主要DBに載らず、政策判断の根拠になりにくい |
| 編集体制・過去の評価 | 編集長はJames Lyons-Weiler氏 | 過去にワクチン関連論文の撤回歴あり | 査読の堅牢性・中立性に疑問 |
| 公的評価との整合性 | 「承認取消・回収」を要求 | 厚労省・日本感染症学会は「承認維持可能」と判断 | 公式データ解析と一致せず |
| 大規模独立研究との比較 | 個別の症例や論考を強調 | 国際ネットワーク解析では「大規模な安全性破綻なし」 | 大規模コホートとの齟齬があり、合意形成につながりにくい |
まとめると、ワクチン問題研究会は「専門家が実名で問題提起する場」としての意味を持つ一方、発信のプラットフォームや査読体制、公的評価や大規模研究との整合性といった面で限界があり、承認取消や回収といった政策要求を動かす決定打にはなりにくいと言える。
ただし、十分に研究が進んでいない接種後症候群(PVS)を可視化する役割は担っており、その点に存在意義があると整理できる。
2.過去の薬害事件との比較
日本の薬害史は、いくつかの大きな事件を経て制度改革を重ねてきた。
- サリドマイド事件(1960年代)
:睡眠薬として投与された結果、多数の先天性障害児が発生。
催奇形性試験の義務化につながった。 - SMON事件(1970年代)
:整腸剤キノホルムが神経障害を引き起こし、社会問題化。
厚生省の対応遅れが批判され、副作用被害者救済制度が創設された。 - HIV汚染血液製剤(1980年代)
:非加熱血液製剤による感染被害。刑事責任追及と大規模補償へ発展。
これらはいずれも「単一の薬剤が投与された患者個人に直接的な被害を与えた」事件であり、焦点は医薬品の承認過程や安全性確認の不備にあった。
一方で、COVID-19ワクチンは世界的パンデミックという背景のもと、集団全体の危機を防ぐための“特例承認”が行われた。一般的な「薬害事件」とは異なると言える。
危機対応 vs 個人選択のジレンマ
公衆衛生危機対応
- ワクチン導入は「感染拡大抑止」「医療崩壊防止」を目標として推進された。
- 不確実性が残る中でも「行動しなければ大量の死者が出る」可能性があるという前提で、迅速な承認と市販後監視という“走りながら安全性を確認する”方式が採られた。
個人の選択
- 個人にとっては「自分が接種してどんなリスクを負うか」という視点が中心。
- 接種を選んだ人は「感染による重症化回避」を優先し、接種を見送った人は「副反応や長期的影響の不透明さ」を重視した。
スケールの違い
- 過去の薬害:リスクは個人レベルで完結。
- コロナワクチン:接種有無の積み重ねが社会全体の感染動態や重症者数に直結する。
つまり、「個人の自由」と「社会的利益」が衝突する場面が多発した。
違いをどう見るか?
- 過去の薬害事件は「承認の不備による個人被害」
- COVID-19ワクチンは「不確実な中での社会的危機対応」
こうした違いを踏まえれば、COVID-19ワクチンをそのまま「薬害の再来」と呼ぶのは単純化に過ぎる。しかし、制度への不信や過去の薬害の記憶が人々の受け止め方に影響を与えているのも事実だ。その結果、ワクチンをめぐる社会的な立場は大きく三つに分かれる傾向が見られる。
3.「反ワク」「信ワク」「陰謀論」の三つの立場
一般的な「薬害」とは異なるため、人々の不信や経験からワクチンをめぐる三つの立場に分けられる傾向にある。
| 観点 | 反ワク(批判的立場) | 信ワク(全面受容) | 陰謀論的立場 |
|---|---|---|---|
| リスク認識 | 副作用・長期的影響を重視 | 感染症リスク・集団防衛を重視 | 「本当のリスクを隠している」と考える |
| 制度への信頼 | 国・製薬企業を疑う | 政府・学会の判断を信頼 | 「政府・企業が裏で操作」と想定 |
| 根拠の扱い | 副作用報告・被害者証言を重視 | 臨床試験・大規模統計を重視 | 都合の良いデータや噂を選択的に利用 |
| 個人 vs 集団 | 個人の安全・自由を優先 | 集団免疫・社会的利益を優先 | 個人が犠牲にされる物語を強調 |
| 物語 | 「安全性が十分に確認されていない」 | 「科学と社会を守るために必要」 | 「闇の勢力が人々を支配している」 |
- 反ワクの抜け落ち:感染拡大や医療崩壊といった社会的リスクの視点。
- 信ワクの抜け落ち:制度不信や過去の薬害の記憶。
- 陰謀論の位置づけ:両者の隙間を“物語化”して埋める役割を持つ。
ただし、実際には完全にどれか一方に当てはまる人ばかりではなく、その間を揺れ動く人も多い。
この三者は「賛成/反対」の二項対立ではなく、それぞれに“見えているもの”と“見えていないもの”がある。ここを理解することで、単なる対立を超えて「なぜ意見がかみ合わないのか」を説明できる。
4.まとめ:信頼の空白をどう埋めるか
「一般社団法人ワクチン問題研究会」の要望は、mRNAワクチンの承認取消と回収を求めるというものであった。しかし、発信先の位置づけや学術的評価の差異、公的機関との整合性を踏まえると、その主張が直ちに政策を動かす力を持つとは言い難い。
同時に、過去の薬害事件と今回のワクチン政策を単純に同列視することも適切ではない。
過去は「個別薬剤の安全性不備による個人被害」だったのに対し、COVID-19ワクチンは「社会全体の危機対応」という性格を持っていた。ここには個人の選択と集団への影響のスケールの違いが存在する。
反ワク・信ワク・陰謀論、それぞれの立場は異なるが、共通しているのは「信頼の空白」に直面していることだ。科学的エビデンスが更新されるよりも早く、人々の不安や不信感は広がる。
その隙間を埋めるように陰謀論が語られる。
次の感染症危機に備える上で重要なのは、「迅速な対応」と「慎重な安全性確認」のバランスをどうとるか、そして「個人の納得感をどう確保するか」である。
承認取消か全面信頼かという二分法ではなく、不確実性を前提にした透明な情報公開と、個人・社会双方に配慮した制度設計が求められている。
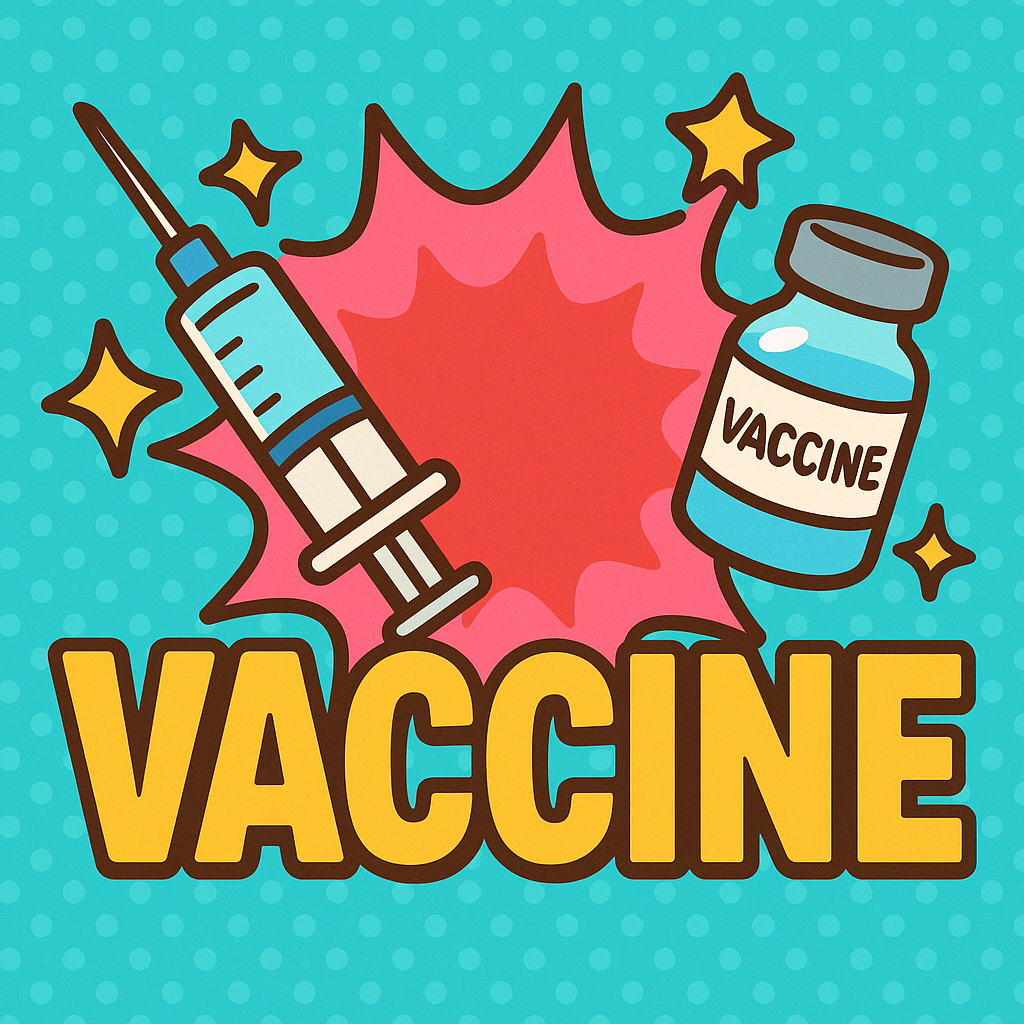

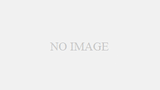
コメント