中東のニュースを見ていてふと感じた。
祈る人々の背景には、いつも対立がある。
「信じる」って、そんなに複雑なことなのだろうか?
そんな疑問から始まった、いつものふたりの会話。
今回は、宗教、国家、そして人間の“欲”について、かえるくんとぺんしるくんの対話を見てみよう。
信仰の名のもとに争いは起きるのか?ぺんしるくんとかえるくんの雑談

イランの指導者が「決して降伏しない」って言ってたけど、停戦して一か月が経ったな
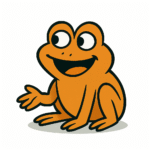
ニュースで初めて見たとき、
ターバン巻いててアラジンかよって思ったけど威厳があったわ
ハメネイ師だっけ…?(※1)あれも宗教的な意味があるんやろな
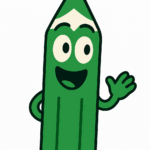
イランは大統領もいるけど、最高指導者が一番権力持ってるんだよ
大統領は行政を回す役で、国の方針は指導者は握ってるって感じかな

なんや、それ
将軍と天皇が分かれてた昔の日本みたいやな(※2)
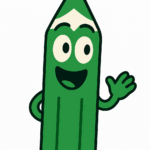
近い
けど、実際は将軍と天皇を足して、さらに宗教指導者も混ぜたようなトップオブトップって感じかな
イスラム革命(※3)前はアメリカ寄りの政権だったんだけど、それを倒して今のイスラム教中心の体制ができた
今の最高指導者は1989年からずっと変わってない

ニュースではハメネイ師しか見たことなかったから、
大統領がおるって聞いて指導者のほうが偉そうやなって思ったけど
…ほんまに偉いんやな
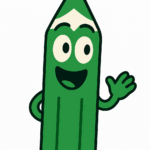
よく観てるな
でも「偉い」ってより、「動かない」ってのが正しいかも
国の核の部分として置かれてる存在やね

でもさ…「三つの宗教の聖地」(※4)なんて、最も平和であるべき土地でずっと対立してるなんて悲しいことやな
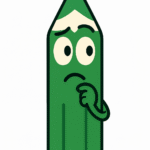
宗教“だけ”が原因って短絡すると見誤る。領土・民族・安全保障・歴史の遺産とか、非宗教もガッチリ絡んでる
“みんな自分中心で”という前提の上での平和が欲しいんや
それは国も、宗教も、個人も同じやね
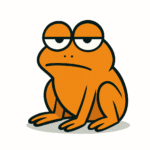
でもさ、それって“天国への道”とはちゃうやろ?
信仰って、そんな利己から出発してええもんなん?
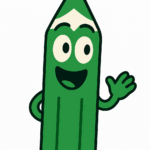
現実には、マフィアにすら“国を愛してる”って言う奴はいる
愛国を掲げて犯罪行為
矛盾やけど、それが現実ってこと
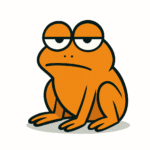
結局、宗教とか信仰って“人の上に立ちたい”っていう浅ましい欲に負けてる時点で、
それってもう信仰ちゃうやん
欲を“神の意志”みたいに包んでるだけなんやないか
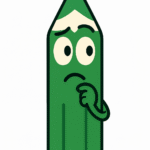
そこは分けたほうがいいね
信仰は個人だし、宗教は共同や制度、国家は別物
混ざると、言葉は同じでも動機が変わる
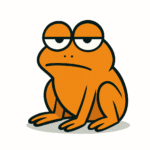
でも、“隣人を愛せ”(※5)って言ってるのに、愛してないやんって場面、山ほどあるやん

「隣人を愛せ」はキリスト教やユダヤ教で有名な表現やな
イスラムにも“慈しみ(ラフマ)”や“善行”(※6)を重んじる規範がたくさんあるよ
ただ、誰を“コミュニティの内側”とみなすかは時代や法学派、政治状況で揺れる
そこでまたギャップが生まれる
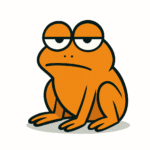
イスラムの源流ってキリストやろ? (※7)
それなら本質的には“愛と赦し”が基盤に——
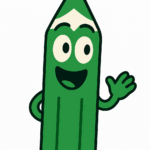
それは勘違いしてるね
イスラムはアブラハム系一神教の一つで、ムハンマドに下った啓示が起点
イエスは“預言者”として尊重されるけど、神そのものではないんよ
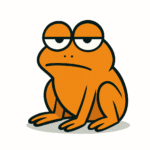
なるほど、源流の勘違いしてたわ
でも、教義に縛られて本質を見失ってるのは間違いないんとちゃうか
“異教徒だから”、“他者だから”、“自分だから”って理由で傷つけるなら、
それはもう信仰やない
キリストが十字架を背負ったのは、世界をより良くするためやろ?
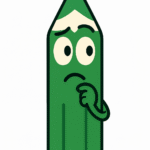
……かもしれん
でも、信じること、信仰すらなければ、もっと悪かったのかもしれん

なら、なおさらやろ
より一層、悔い改めよ

争いの根っこを、人は信仰に押し付ける
でも、”自分が正しい”と信じる心が、一番頑固なのかも
それもまた、ひとつの”信仰”かもしれないね
まとめ
イランにおいては、大統領よりも宗教的権威を持つ「最高指導者」が実権を握っており、その存在は政治・宗教・国家体制すべての根幹をなしています。
この体制は1979年のイスラム革命によって成立し、アメリカ寄りの王政から一転、イスラム神権政治へと移行しました。
彼らは、宗教的な矛盾や暴力の背景にある「人間の欲」や「国家の都合」が浮き彫りにされ、「信仰とは何か」「宗教と制度をどう切り分けるか」といった根源的な会話をしています。
「隣人を愛せ」「慈しみを大切にせよ」と説かれる宗教倫理が、なぜ現実には対立や暴力へと変質してしまうのか。
信仰が人を救うものならば、なぜ争いは絶えないのか。
信仰のない日本でわたしたち自身、何を「信じる」ことができるのでしょうか?
会話補足
※1.ハメネイ師
イランの最高指導者アリー・ハメネイ師(Ayatollah Ali Khamenei)は、1989年から現在までその地位にあるイランの最高権力者。
「師(し)」は「アーヤトッラー」というイスラム教シーア派の高位聖職者の訳語。ターバンは宗教的権威の象徴でもあります。
※2.将軍と天皇が分かれてた昔の日本
日本では江戸時代など、「天皇は象徴的存在」「将軍は実権者」という構図がありました。
イランの場合は、これに宗教指導者としての側面も加わり、信仰・政治・司法を束ねる存在として最高指導者が位置づけられています。
※3.イスラム革命
1979年、イランでパフラヴィー国王の親米・世俗政権を倒し、イスラム指導者ホメイニを中心とするイスラム共和国が樹立された事件。
これにより、イランは神権体制(宗教指導者が最終権限を持つ体制)へと大転換しました。
※4.三つの宗教の聖地
エルサレムなどの地域は、ユダヤ教・キリスト教・イスラム教のいずれにとっても重要な宗教的聖地です。
この地域の帰属を巡って長年にわたって対立が続いており、「宗教戦争」と誤解されがちですが、実際には宗教以外の要素(領土、政治、民族など)も深く絡んでいます。
※5.隣人を愛せ
「隣人を愛せ」は旧約聖書(レビ記)や新約聖書(イエスの教え)に登場するユダヤ教・キリスト教共通の倫理観。
イスラム教でも、他者への思いやりや善行を重視しており、似たような規範があります(次の※6参照)。
※6.ラフマ(慈しみ)や善行
イスラム教では、神の最も頻繁に使われる概念が「ラフマーン(慈悲深い)」。
「隣人に善くせよ」「弱者を助けよ」という命令がコーラン中に繰り返されており、社会的徳目としての“善行”は非常に重視されています。
※7.イスラムの源流について
イスラム教はアブラハムを共通の祖とするユダヤ教・キリスト教と並ぶ一神教ですが、直接の起源はムハンマドへの啓示(610年頃)とされています。
イエス(イーサー)は預言者の一人として尊重されていますが、キリスト教のように「神の子」とはされていません。

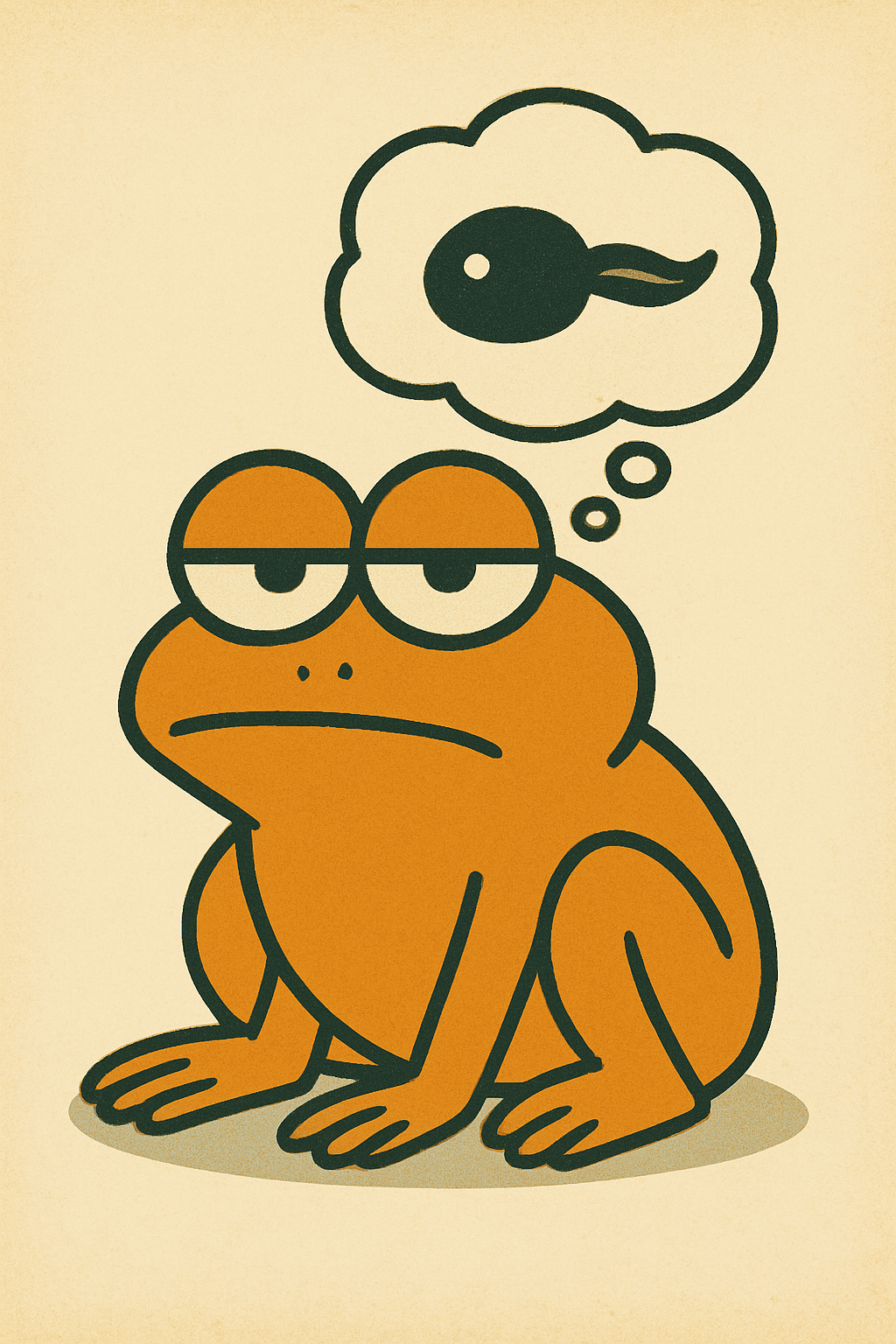

コメント