いつものように始まった、ペンシルくんとカエルくんの朝の会話。
金色のスマートフォンに関するニュースが話題に上がると、自然とその”持ち主”について語られることになった。
軽い雑談のように見えて、この会話は次第に、「トランプとは誰だったのか?」「アメリカとは何か?」という問いへ移っていく。
その問いは、外側の派手さから内側の空虚さ、そしてそれを取り巻く社会と国家へと滑らかに沈んでいく構造を持っていた。
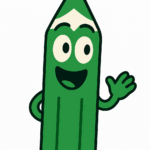
トランプがモバイルサービス始めたらしいよ!スマホ端末は金ピカ!
なんか…欲しくなるよな(笑)
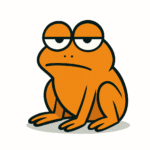
勝手に買えよ
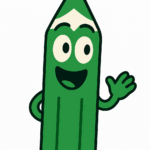
でも、トランプって成金っぽくない?
トランプって、もともと金持ちの家に生まれてるのに、あえて成金趣味なのが不思議なんよな

中身が空っぽだから、外側の“記号”に惹かれるんやろうな
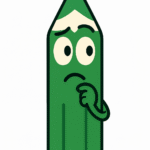
…朝から核心突くやん
でも確かに、そういう人っているな
“見た目”で自分を作ろうとする人

彼、ずっと“誰か”になりたかったんやと思うよ
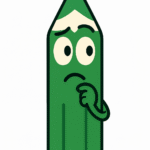
でも、そんな彼をあれだけの人が支持したってのが不思議だよなあ…

彼は金持ちだけど、自分の手で金持ちになったわけじゃない
親の財産から始まった男が、“本物の指導者”に憧れて、自分をその像に当てはめたんや
1期目初期は習近平と、2期目初期はプーチンと仲良さそうに見えたが”憧れ”が入っていたのかもな
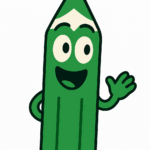
なるほど…
見た目や振る舞いはリーダーっぽくしてるけど、中身は借り物なんやな
親の金で始まった人生だと、どれだけ外側を飾っても根っこが埋まらない感じ…あるかもしれんな

だからこそ、金や権力を飾り立てるような趣味になるんや
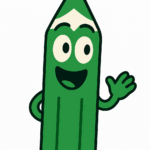
それって、ある意味で“キャラクター”やね
金と権力以外に、トランプ“自身”っていう核が人生で見つからなかったのかもな
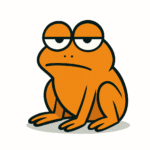
それは、彼そのものが“USA”であるということや
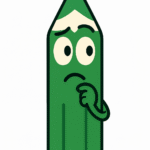
うん…叙情的に言えば、そういう空虚さこそが“アメリカらしさ”になったのかも
金と記号だけで満たされた国…資本主義の終点にある、派手で空っぽな器
そう考えると、トランプは最もアメリカ的な大統領だったのかもしれんな
ペンシルくんとカエルくんの会話は、トランプという人物への違和感から始まり、その内面の構造へと入り込んでいった。
彼の成金趣味、演出過多なキャラクター性、それらは単なる嗜好ではなく、「中身を埋めるための記号化」だったのではないか。
そして、その空虚さを人々が支持したという事実は、トランプ個人の問題ではなく、社会全体が“演出された人物”を求める構造に陥っていることを示していた。
この会話の中で浮かび上がったのは、「空虚と記号が価値になる時代」における、ひとつの象徴的な存在だった。
トランプという“人物像”
1. 自己を“演出”した人物
トランプは、自らの人生を“物語”として演出した人物だと言える。
内面の確信よりも、「強さ」「富」「敵への攻撃性」といった記号的要素で自己を補強し続けてきた。
本物であることより、“本物っぽく見えること”を優先した結果、外側だけが膨張していった。
そして彼は、そうした“本物っぽさ”を 他者に投影することで模倣しようとしていた。
1期目初期には習近平と、2期目初期にはプーチンと、まるで仲の良さを演出するかのように接近した。
それは外交戦略の一環でもあったが、どこか“強さへの憧れ”が混ざっていたようにも見える。
他者を“自分のロールモデル”として仮置きし、それに倣うことで、自分自身の物語を現実化しようとする構造。それこそが、トランプという人物の根源的な「空虚の補完方法」だったのではないだろうか。
2. 空虚を抱えたキャラクター
トランプの人生には、一貫して「自己を埋めるための象徴」が必要だった。
金、ブランド、果てには“トランプ”という名前自体をブランドにし、家族の名前も商標登録した。
彼は、「自分とは何か」を見つけられないまま、外側で“トランプ”を作り続けるしかなかった。
何者かでありたいという衝動。
けれど、本質的な“自分”が不明瞭なまま進んでしまった結果、演出だけがどんどん肥大化した。
3. 社会が求めた“空虚な強者”
驚くべきは、それでも多くの人が彼を支持したという事実だ。
それは、彼が“異質”だから支持されたのではなく、むしろ「わかりやすく、記号的で、敵をつくりやすい存在」だったからこそ、支持が集まった。
つまり、空虚さそのものが、社会にとって“消費しやすい記号”になっていたのだ。
「中身のある人物」よりも、「演出された強さ」を求める社会の構造が、彼というキャラクターを押し上げたとも言える。
4. トランプ=アメリカという寓話
カエルくんが最後に言った「彼そのものがUSAである」という言葉は、象徴的だった。
空っぽで、金と記号で飾られ、内面が曖昧なまま支持される存在──
それは、アメリカという国が内包してきた、資本主義の矛盾そのものでもある。
トランプという人間を見つめることは、同時にアメリカという国の現在地を見つめることでもある。
そして、わたしたち自身が「何に惹かれ、何を演出し、何に期待してしまうのか」を問い直すことでもある。
まとめ
トランプを笑うことは簡単だ。
だが、なぜその空虚さに惹かれてしまうのか──それは、わたしたち自身の側の問題でもあるかもしれない。
「本物の中身」よりも「それっぽさ」に惹かれる社会。
もしかしたら、ペンシルくんとカエルくんの会話が映していたのは、トランプという一人の人間を通して、現代そのものの“かたち”だったのかもしれない。



コメント