「コメの輸入にかじを切った事実はない」
2025年6月、小泉進次郎農水相はこう述べた。
一方で、その数日前には、こうも発言している。
「緊急輸入も含め、あらゆる選択肢を持ちたい」
国民の怒りは大きく、与党内からも「主食を外国に頼ってはいけない」との声が上がった。
だが、この一連の発言には、ある本質的な“すり替え”が潜んでいる。
小泉氏はこうも述べているのだ。
「かじを切っているのは政府ではなく、“民間”だ。」
ここに、現代日本が抱える根源的な問題がある。
政治の責任ではないと言いながら、市場(民間)が主食を決める構造がすでに成立している。
そしてその構造をつくってきたのは、我々国民自身が選び続けた「安さ」だったのだ。
1.その丼、誰が育てた米か知ってますか?

どれだけ「国産米を守れ!」と叫んでも、現実ではそうなっていない。
外食チェーンでは、仕入れコストに合わせて米の品種や品質が調整されている。
その結果として、外国産米や“国産ブレンド米”が日常的に使われているのが実態だ。
だが、ここで言う“国産”というラベルが、何を意味するのかは実にあいまいだ。
銘柄や産地の指定はなく、単に「日本で生産された」とされる米。
複数の産地や格下等級が混ざっていても、“国産”と表示できてしまう。
それでも人々は、それを気にしない。なぜなら、価格で選ぶからだ。
どんな産地のどんな味かではなく、いくらか。
私たちが毎日繰り返しているこの選択は、まぎれもなく“財布で投票する”という行為そのものだ。
たとえば、松屋。
公式サイトでは、店舗ごとに使用している米の原産地を調べることができる。
しかし、いくつかの店舗を調べてみても、「国産」とだけ書かれたシンプルな表示は見つからず、外国産との併記やブレンド表記が目立つ。
たとえば、吉野家。
「国産米を中心に、外国産をブレンドした米を使用しています」と明記されている。
あの400〜600円の価格帯を守るために、いったい何が切り捨てられてきたのか?
産地か? 品質か? それとも、生産者自身か?
そして、その選択を続けてきたのは、政治家ではなく、我々の“財布”であり、“日々の選択”だったのではないか。
あるいは、選挙で選んだ“政治家”によって生まれたと言ってもよい。
だがその政治家たちもまた、国民の消費行動と支持率を見ながら動いている。
さらに言えば、もはや政府が主導しなくても、価格競争にさらされた民間企業が“外国産米”を選ばざるを得ない仕組みが、すでに完成しているのだ。
政治家がどれだけ「輸入には踏み切っていない」と弁明したとしても、民間の選択は、資本原理と市場価格に従って進行していく。
そこにはもう、「主食は国産であるべきだ」という建前は通用しない。
2.農業はもう「守られる産業」ではない
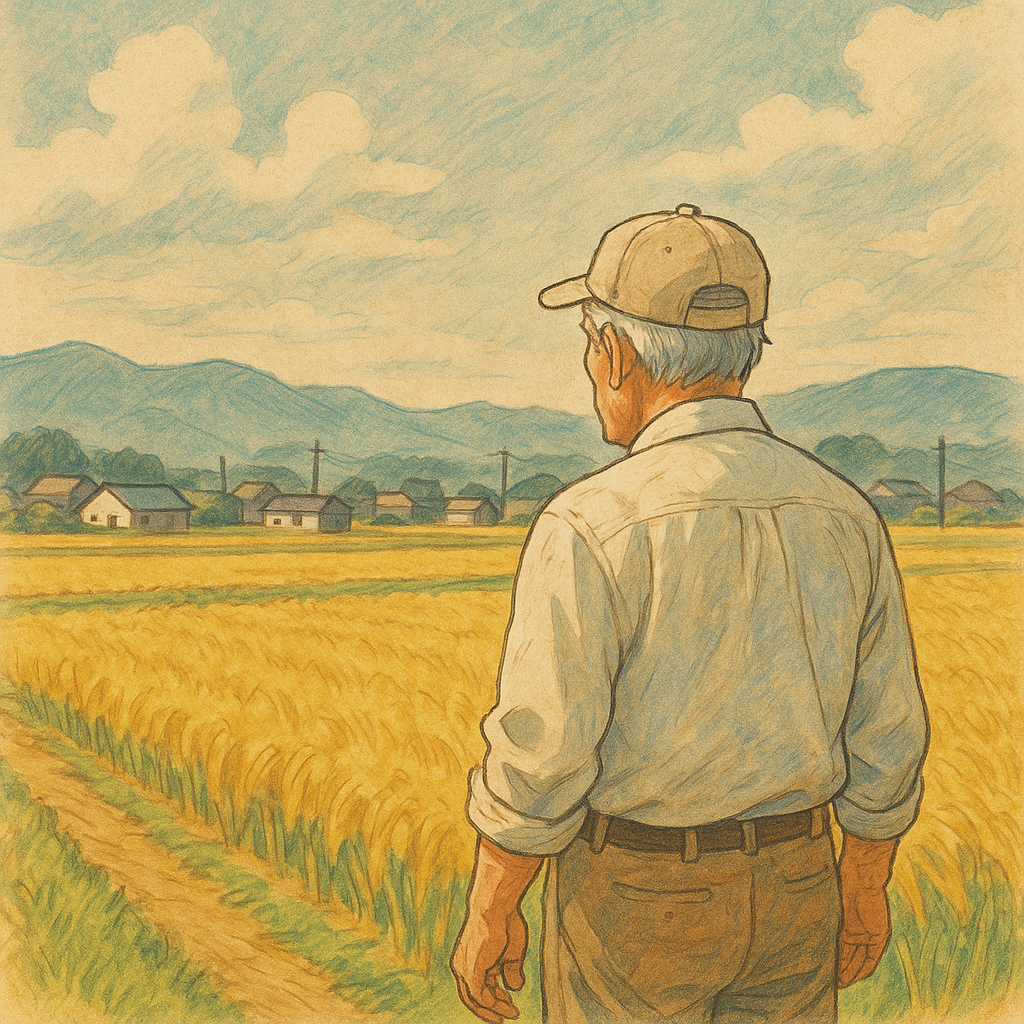
中国の皇帝が「農は国の本(もと)なり」と言ったように、日本においてもかつて農業は“国の根幹”と呼ばれた産業だった。食料を自国で賄うことが安全保障そのものであり、農村は「票田」としても政治的な力を持っていた。
しかし、資本主義の波はその足元を静かに、そして着実に削ってきた。
農家の平均年齢は約68歳。後継者不足が叫ばれて久しいが、それでも農家の戸数は減り続けている。
生き残るのは、経営能力の高い農業法人や大規模経営体のみ。
農地を拡大し、法人化し、コスト管理と収益性を徹底した“企業農業”だけが資本主義の土俵に立つことが許されているのだ。
つまり、資本主義のルールに適応できなかった小規模農家は、競争から脱落する運命だった。
もちろん、政府が何もしなかったわけではない。
戸別所得補償制度や価格安定政策など、支援策は打たれてきた。
だが、それらはどこか「延命装置」のように作用し、農業を“持続可能な産業”ではなく、“守られるべき遺産”へと変えてしまった。
そしていま、価格が高騰すれば「外国産米」というカードが切られる。
たとえそれが“緊急措置”という名目であったとしても、その先にあるのは、「輸入自由化の既成事実化」にすぎない。
小泉進次郎の「かじを切っていない」という発言は、その象徴だ。
政府は“指示”せず、“否定”もせず、「あらゆる選択肢を持つ」と言いながら、市場が自然と輸入に向かうことを容認している。
つまり、「農業はもう、守られない」というより、「守られているように見せかけながら、実際には“見捨てられている”」
それが、今の日本における農業の立ち位置なのだ。
3.猫が配膳する社会で、何が終わろうとしているのか
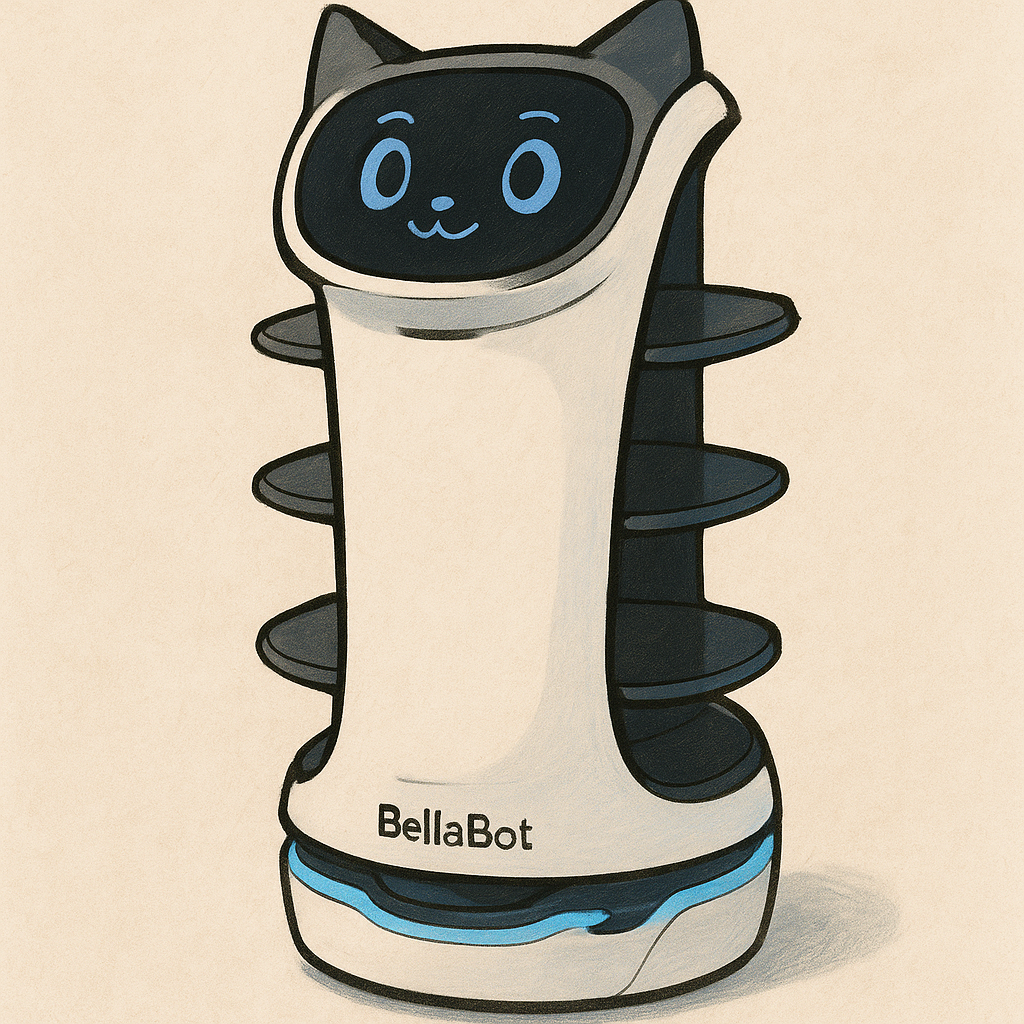
農業(1次産業)が見捨てられつつあるとすれば、次に奪われるのは、果たして誰の仕事だろうか?
そのヒントは、ファミレスを静かに歩く猫型ロボットにある。
「ベラボット」や「Servi」と呼ばれる自律走行ロボットが、注文された料理をテーブルまで運ぶ。
かわいらしい見た目と滑らかな動きに、子どもは怖がったり、手を振ったり―――そんな光景は、もはや珍しいものではなくなった。
最初は“話題づくり”かと思われていたこのテクノロジーは、今や「人件費の削減」「人手不足対策」「感染症対策」などの名のもとに、“当然の効率化”として導入されつつある。
だが、これは単なる便利グッズの話ではない。
ここにあるのは、
「3次産業=人の感情・気づき・対応力が価値だった領域」さえも、資本主義の論理のもとで“切り詰められる”段階に入ったという事実だ。
製造業(2次産業)が機械に置き換えられたのは、もう何十年も前の話だ。
ロボットが溶接をし、部品を秒単位で処理する。そこに“人間らしさ”は求められなかったし、むしろ排除されていった。
それに比べて、サービス業(3次産業)は長らく「人間でしかできない領域」だと信じられてきた。
「ありがとう」と言う、「気づく」「笑顔を向ける」。
それはAIにもロボットにもできないと思われていた。
だが今や、セルフレジやハーフレジが会計をこなし、モバイルオーダーで店員に飛ばし、猫型ロボットが料理を届ける。
人間の“手”も“声”も、確実に要らなくなり始めている。
この流れを見て、私たちは考える必要がある。
農業のように、「効率が悪い」とされて切り捨てられた先にサービス業さえも“非効率なもの”として削られていく時代が来ている。
猫が配膳するというのは、単なる可愛げのある未来ではない。
それは、かつて“人の存在が前提だった産業”が、資本主義によって切り崩されるスタート地点に立ったことを示している。
4.資本主義は、どこまで人間を削るのか
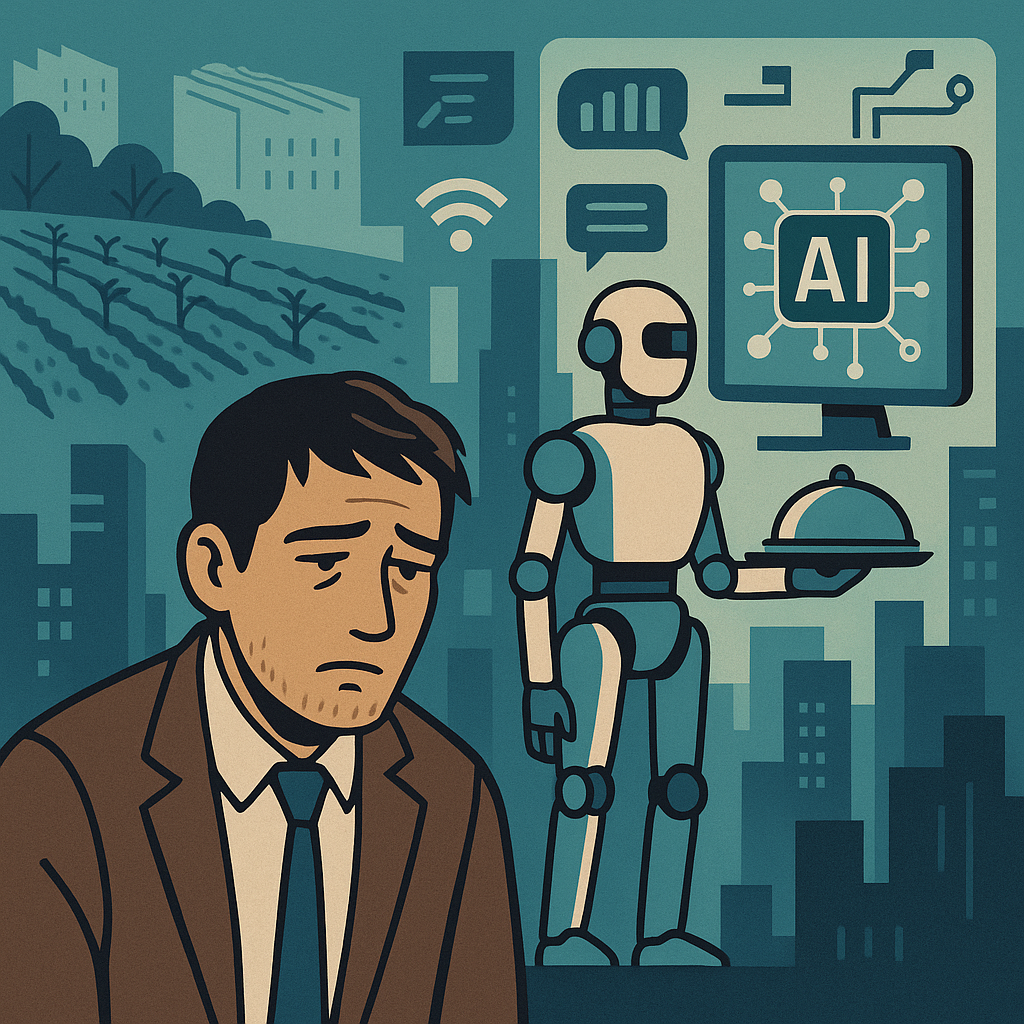
農業が切り捨てられ、サービスは機械化し、それでも資本主義社会は止まらない。むしろ「効率化」という恩恵に、人間は疲弊しながら飲み込まれていく。
資本主義とは、「速く、安く、正確に」を極限まで求める仕組みだ。
その論理において、もっとも非効率な存在が“人間”である。
私たちは、どこに存在すればいいのだろうか?
情報社会、デジタル経済、そしてAI。これらが支配する現代は「4次産業社会」と呼ばれる。
GAFAに象徴されるように、価値は「物を作ること」から「情報を操ること」へと移行した。
データを蓄積し、解析し、利益に変える。
ユーザーのクリック、位置情報、購買履歴、それらすべてが「資源」になり、見えない労働=生活そのものが搾取対象になったとも言える。
機械とアルゴリズムの支配力は人間を圧倒し始めている。
人が書いた記事より、AIの方が速く、安く、より正確だ。顧客対応も、文案作成も、戦略提案すらもAIがこなす。かつては、”頭脳労働”とよばれていたものすら、奪われつつあるのだ。
たとえば、企業が導入を進めている分野は、以下の“知的で定型的な業務”である。
- 自動翻訳
- 文書作成補助
- プログラミング
- カスタマーサポートチャットボット…etc
つまり、大学卒のスキルですら、資本主義のコスト削減競争の中では“置き換え対象”になった。
人件費はコストだ。そしてAIは、ほぼ無料で稼働し、24時間休まない。
かつて「人間にしかできない」とされた仕事は、効率・正確さ・維持費の観点から、“非合理”とされる時代に入った。
「手」だけでなく、「頭脳」までも資本主義に置き換えられつつある。
そしてこの動きは、農業や配膳以上に静かに、しかし急速に進んでいる。
まとめ
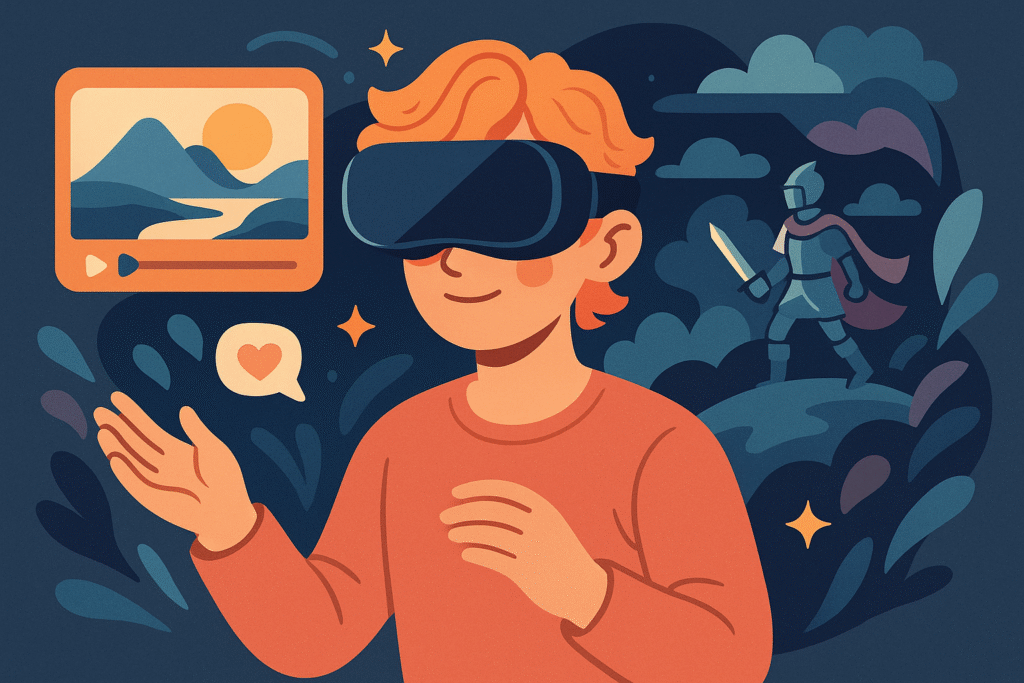
1次産業(農業)、2次産業(製造)、3次産業(サービス)、4次産業(情報処理)と、人間の仕事は段階的に”奪われ”、人の仕事は”圧縮”されてきた。
資本主義は、合理性と効率を突き詰めた先に、人間の手を奪い、足を奪い、頭脳を奪おうとしている。その結果、農業は見捨てられ、製造は無人化され、サービスは猫に任され、意味さえもAIが作る時代に突入した。
だが、それでも選ぶのは私たちだ。
1杯の牛丼、1袋のブレンド米、1回の非対面オーダー。
その一つひとつが、私たちが「どんな未来を望むか」の意思表示なのだ。
政治家を批判するのは簡単だ。
けれど、その政治家を選び、“消費”を続けているのは、他ならぬ私たち自身である。
AIが意味を作り、ロボットが仕事を奪い、資本主義が「正確で効率的な世界」を完成させようとする中、それでも最後に残るのは”何を選ぶか”というのは人間自身だ。
文化や伝統は、そもそも非合理で、手間がかかり、儲からないものだ。
それでも人間は、そうしたものを守り継承してきた。
「意味を生きる」という営みが、人間だけに残された仕事だとするなら。
それを守るのは、AIでも市場でもない。
私たち一人ひとりの選択と、継承する意思なのかもしれない。




コメント