YouTubeを眺めていたところ、ひろゆき氏の切り抜き動画がおすすめに表示された。
再生してみると、今話題になっている「備蓄米問題」について語っていた。
要点はこうだ。
「備蓄米は5年間保管されるが、品質劣化のため、その後は家畜用として使用される。
これは毎年繰り返されている“制度上のルーチン”にすぎない。」
その上で、国民民主党の玉木代表が「餌米」といった表現が批判されたことに対し、ひろゆき氏はこう指摘する。
「実際そうなのに、表現だけを問題視するのはおかしい」
「事実を述べているだけなのに、それを“失言”と受け取る人は、制度の実態を知らないのではないか」
つまり、「感情的・表面的な反応が問題」であり、「もっと冷静に、事実を見るべきだ」というスタンスだ。
また、国民民主党に対しては「偏差値60以上の人しか理解できない政党」と皮肉交じりに述べており、高度な情報理解に基づいた“正論”を述べただけだという、ある種の擁護にも聞こえる。
制度としては間違っていない。
だが、問題は正しさそのものではなく、共感性ではないだろうか?
でなければ、炎上なんてしていない。
この”家畜用の米”問題に込められていたのは、“事実“と“感情“のズレではないだろうか。
1.ずれているのは誰か?
制度の説明としては正しいし、それは疑いようのないことだ。
だが、その言葉が発された「場」と「タイミング」、そして「語り口」には、多くの人が違和感を覚えた。
「家畜用」と言えば、制度的には米の用途区分を正確に表している。
しかし、現在の社会状況から考えると物価高騰や米不足は家計への圧迫を前にすれば、それは「食べ物が足りない」と感じる生活者にとって、どこか冷たく、線を引かれたような言葉に感じてしまう。
たとえば、
医者がガムでも噛みながら、診察室で「あー、もうすぐ死にますねw」と言ったらどうだろう。
いくら事実でも、「オイ、ちょっと待て、治療法はないのか?」と言いたくなるはずだ。
同じように、「これは家畜用になる米なので――」と制度的には正しくても、生活者にとっては「明日食う飯が高いだわ」という怒りだけが残る。
問題は、正しさではなく“共感の温度差”だ。
実際、周囲でも「家族4人で毎月30kgの米を消費する」という家庭もある。
毎日朝昼晩、主食として米を食べると、それくらいはすぐに消えていくようだ。
かつて30kgで1万円少し程度だった米は、現在では2万円を超えることになる。
2年足らずで、ほぼ倍。これは、単なるインフレの域を超えている。
長年の農政のツケ、担い手不足、減反政策の矛盾、そして制度の疲弊がもたらした結果だ。
制度の中にいる政治家には、これらは“数字”に見えるかもしれない。
だが、食卓にいる市民にとっては、“怒りの理由”そのものである。
このズレは、ただの“失言”ではない。これらは各立場の分断を映しているにすぎない。
- 政治家は「制度で語る」
- 有識者は「データで語る」
- そして市民は「生活で語る」
全員がそれぞれ正しいことを言っている。
だが、立場によって意見とは異なるもの。だからこそ、誰の意見も、相手には届いていない。
”孤立した正論”が並ぶだけの空間となっているのだ。
この状況を「誰が悪いか」で片付けることはできない。
だが確かなのは、この“ズレた空間”の中で、声を上げた人だけが評価され、そのもののツケはまた、うやむやにされようとしている、ということだ。
2.進次郎、動く
炎上の始まりは、ある一言だった。
江藤拓・元農林水産相が佐賀市で開かれたパーティーの壇上で、こう発言した。
「私はコメを買ったことがない。支援者の方がたくさんくださるので、売るほどある」
現実離れしたこの発言に、批判が殺到。
「アホなのか?」「こんな無神経な発言をするなんて、炎上狙いか?」
炎上は瞬く間に広がり、江藤氏は更迭となった。
そして、その“空いたポスト”に任命されたのが、小泉進次郎だった。
政治的には、目の前の火消し役として送り込まれたとも言える。
だが、江藤拓・元農相の炎上がなければ、備蓄米の放出は未だに実現していなかったかもしれない。
進次郎は、着任直後に備蓄米の「随意契約による放出」を発表した。
現場の混乱や米価高騰への応急処置として、制度を超えた“裁量的対応”に踏み込んだのである。
この判断に対しては、党内からも異論が出た。
野村元農相は「党の農林部会に諮っていない」としてルール違反を指摘したが、進次郎はこう反論する。
「いちいち党に諮っていたら、スピード感を持った政治はできない」
「私は大臣として責任を持って判断したので、これがルールだと思う」
この発言は、「制度より現場」「ルールより判断」という彼のスタイルを明確に示すものだった。
結果、“評価されたのは進次郎だった”。
「やるべきことをやった」「スピード感があった」「実行した」
他の政治家が“制度の説明”に終始するなか、唯一“市民の感情に反応した政治家”として映ったのである。
だが、忘れてはならない。
この米価高騰や供給不安は、ここ最近始まった問題ではない。
農業従事者の高齢化、担い手不足、減反政策の矛盾、気候変動などの複合要因は、少なくとも2年以上前から指摘されていた。
そしてそれを放置してきたのは、自民党政権であり、進次郎自身もその中にいた。
火をつけた消防団の中から、バケツに水を汲んで走り出した者が拍手されている。
構造的には、そういう話だ。
小泉進次郎個人を責めたいわけではない。彼が「動いた」こと自体には意味がある。
だが、その行動だけが評価され、構造そのものへの責任が問われないまま終わってしまうのならば、また同じ火事が、別の場所で起きるだけだ。
必要なのは、火を消す人間ではなく、火事を未然に防げる“見直し”そのものである。
3.なぜ今なのか?
米価の高騰は、けっして突然始まったわけではない。2022年頃からすでに業界や現場では兆候が見られていた。農家の減少、担い手不足、気候変動、そして長年の減反政策の余波。
いわば、ジワジワと火種が積み重なっていた。
では、なぜ「今」それが一気に燃え上がったのか。
その背景には、いくつもの“タイミングの重なり”がある。
①江藤元農相の失言炎上
1つ目は先にも書いた通り、佐賀市でのパーティーで江藤元農相が「私はコメは買ったことがない。支援者の方がくださるので、売るほどある」と発言したことだ。
国民の“主食”を軽んじたように聞こえるこの言葉は、たちまち怒りを呼んだ。
この失言が“火口”となって、積もっていた火種に着火した。
② 消費者の“実感”
かつて1万円ちょっとで買えていた30kgの米が、今や2万円を超える。
1日3食米を食べる家庭なら、月に20kgでは足りない。価格が2倍近くになったという実感は明らかだ。
物価高騰、円安、輸送費増、肥料価格の高騰…要因は複合的だが、「米すら高くて買えない」と感じたとき、政治家の「餌米」という言葉は、ただの“説明”ではなく“冷酷”に聞こえる。
③ 選挙の季節
今年は参議院選挙がある。
農村部の支持、地方票、そして“物価への怒り”をどこが受け止めるかが問われる季節だ。
本来ならば、党を挙げて農政の見直しや生活者支援を打ち出すタイミングだったはずだ。
しかし、現実はむしろ逆。
制度派の発言が共感を失い、失言で更迭されたポストに、若手の象徴である進次郎が急遽投入される。
選挙向けに“即応したように見える”が、党内では方針も足並みもバラバラに見える。
その混乱がむしろ、“問題の深刻さ”を裏付けてしまっている。
要するに、これは単なる政策論争ではなく、政策の”言葉”が市民感情とかみ合わなかったから起きた瞬間だった。
4.選挙アピールの空回り
政治家が動くとき、それが選挙前であれば、どうしても「アピール」として見られてしまう。
ましてや今年は参議院選挙。
票になるのか、印象が良いのか?それだけで動機が疑われる空気の中、備蓄米の放出劇は展開された。
しかし、今回の一連の動きが「票につながるアピール」として成立しているかといえば、必ずしもそうではない。
むしろその動きは、政策の根本ではなく“見せ場の演出”ばかりが先行し、かえって政治不信を招いているとも思われる。
1. 足並みの乱れが“統治能力の低さ”に見える
小泉進次郎が備蓄米の放出を決めたことに対し、元農相は「勝手な判断だ」と反発した。
制度上のルールや手続きを無視した形に見えたからだ。
だが、有権者の目に映ったのは、「与党内でまとまっていない」「農政ですら意見が割れる」という印象だ。
選挙前にアピールしたかったはずの「決断力」「スピード感」が、逆に「統治のガタつき」に変換されて伝わる。これでは、アピールがアピールになっていない。
2. 本質を避けた“場当たりの対応”に見える
備蓄米の放出が「応急処置」なのは誰の目にも明らかだ。
米価の高騰や農業構造の疲弊は、何年も前から積み上がっていた課題であり、根本的な見直しが必要とされてきた。
それでも本格的な議論には踏み込まず、“目の前の火だけ消す”動きに終始したことで、進次郎の対応もまた、「構造的課題から逃げた」と映る危険性がある。
市民の一部には「よくやった」と映るだろう。
だが、見ている人は見ている。「これはまた“その場しのぎ”なのでは?」という違和感が残る。
3. 感情との接続に成功しすぎたゆえの“浅さ”の露呈
確かに進次郎は、「動いた人」として評価されている。
行動力、即断、共感、制度の冷たさに反応したことは間違っていない。
だが、その行動が「江藤元農相の炎上」という偶発的な火種によって生まれたものであることは、記憶しておくべきだ。
江藤拓・元農相の炎上がなければ、備蓄米の放出は未だになかっただろう。
つまり、評価されているのは、”変えた人”ではなく、“目立つかたちで処理した人”だ。
4. 評価は一時的、また火は起きる
政治は、火を消す人を讃える。だが、火事を防げなかった構造に目を向けなければ、火は繰り返される。
今回の動きが、単なる“政治パフォーマンス”に終わるのだろうか?それとも、制度疲労に本気で向き合う契機になるのか。それは、ここからの“議論の質”にかかっている。
まとめ:火を消す人と燻り続ける炎
安くなった備蓄米を受け取り、嬉しそうに話す人々。
「緊急輸入も視野に入れる」と語る農水大臣。
「カリフォルニア米、食べたことないけど…まあ、いいか」と並ぶ市民。
その一つひとつは、確かに“努力の成果”に見えるかもしれない。
だが、それは火消しに集中した政治の結果でもある。
米価の高騰は、2年も前から予兆があった。
農家は減り、担い手はいなくなり、減反政策の矛盾は長年放置されてきた。
そして、物価高騰と気候変動がそれに引火した。
進次郎農相が動いたことは褒めるべきことだ。備蓄米を放出し、輸入を検討し、スピード感ある判断を見せた。だが、それが江藤元農相の炎上という偶発的な政治事故のあとに生まれた対応であることを、私たちは忘れてはならない。
拍手されているのは、変えた政治ではなく、破綻を“うまく処理した政治”なのだ。
そして今、“備蓄米が出たから一安心”という空気が生まれようとしている。
しかし、それは本当に安心なのだろうか。
- 政治は変わったのか?
- 国内農業は守られるのか?
- 次の危機には間に合うのか?
そう問われれば、答えはまだ「No」のままだ。
政治は、火を消した人を称える。
だが、燻り続ける炎を消さなければ、評価は積もらず、怒りだけがまた燃え上がる。
今、私たちが見つめるべきは、「誰が動いたか」ではなく、「何が放置され、何が変わらないままか」ではないか。

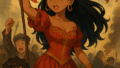

コメント