2025年トランプ政権は2期目となり、再び米中関税戦争を仕掛けた。
だが、両者とも様相が異なっている。
今回の勝者は誰で、どのように、そして誰が崩れるのか?
トランプの演出か、中国の忍耐か、この戦いの行く末が見えてくる。
1.現状のアメリカ:トランプ1.0の“焼き直し”ではなく“拡張”
2025年、トランプ大統領は2度目の大統領任期に突入し、就任からわずか100日で早くもその“手の速さ”を見せつけた。初日には100近くの大統領令を発動し、移民、貿易、環境などあらゆる政策領域でオバマ・バイデン時代の政策を巻き戻す姿勢を鮮明にした。
就任100日演説では、以下のような内容が強調された:
- 「中国がアメリカの雇用を奪ってきた」
- 「不法移民の強制送還で国境は再び守られている」
- 「アメリカ国内の雇用が増加している」
- 「ガソリンや卵など生活必需品の物価が下がった」
- 「関税政策により、世界中の企業がアメリカに工場を戻したがっている」
これらの主張の正誤は、実のところ重要ではない。近年流行しているAIによるファクトチェックが、たとえ一部の誇張や事実誤認を暴いたとしても、“トランプという政治スタイル”が変わることはないからだ。
彼の政治は、常に明確な線引きを行い、敵を作り出し、大衆の感情に訴えかけるスタイルで構成されている。それはもはや「政策」ではなく、即席の「物語」と「演出」である。
現時点での支持率は、歴代大統領の中でも最も低い水準に位置していると言われているが、共和党内での影響力はいまだに健在だ。トランプの支持層は、彼の言葉の真偽ではなく、“誰かが戦ってくれている”という感覚に反応している。
興味深いのは、トランプ大統領がこれまでに4度の破産申請を経験しているという事実だ。
ビジネスパーソンとして致命的とも思えるこの経歴も、支持者からすれば“それでもなお這い上がってきた男”として映る。
つまり、彼の今のスタイルは、過去の失敗すら物語化し、成功体験へと転化していく“逆転劇モデル”なのだ。
今期のトランプ政権は、1期目の繰り返しではない。
それは1期目の延長線上にある「即時成果」と「劇的演出」を重視する強化版トランプ政権であり、任期4年という限られた時間の中で、より“短期成果主義”が加速している。
2.現状の中国:バブル後の日本をなぞりながら、国外に出口を求める経済
中国経済はいま、明確な転換点に立っている。
第1四半期のGDP成長率は5.4%と一見すると安定しているが、これは中国政府が目標として掲げた「5%前後」を意図的に“演出した”数値に過ぎない。実態は、都市部の青年失業率の上昇、不動産市場の崩壊、地方政府の債務膨張など、かつての日本がバブル崩壊後に辿った道をなぞっているような構造不安を抱えている。
だが、中国は日本とは違う。
バブル後の日本が「国内の調整」に集中し、縮小均衡に向かっていったのに対し、中国は経済失速の“出口”を国外に見出そうとしている。
それが「一帯一路」戦略であり、アジア・アフリカ・中東をまたぐインフラ投資の波である。
この戦略は単なる“外貨獲得”ではない。
港や道路、通信インフラなど、“資金回収が二の次でもいい”と割り切った投資が随所に見られる。スリランカのハンバントタ港のように債務返済が不能になった国家が、中国に港の運営権を譲渡した事例もある。
つまり、今の中国は、資金よりも“地の利”と“影響圏”を重視している、と思われる。
これは、経済失速を補う“地政学的投資”であり、かつての日本が決して持ちえなかった、もう一つの「拡張性」だ。
一方、国内では経済格差の拡大と社会の不安定化が進行している。
かつて日本に来る中国人観光客といえば、銀座の百貨店でブランド品を買い漁る富裕層が中心だった。
“爆買い”は中国の経済成長の象徴でもあった。
しかし、最近ではその様相が変わってきている。
2024年11月、東京で開催されたハローキティ展において、限定グッズの“転売”を目的とした中国人グループが殺到し、報道でも話題を呼んだ。
日本に来る目的は「観光」から「仕入れ」へ。
中国の貧乏人たちが、明日の我が身のために日本に仕入れに来ている、というわけだ。
旅行ではなく“在庫確保”、体験ではなく“利益確保”が目的化している。
国家が覇権を求めてインフラを買い漁る一方で、個人はキャラクターグッズや廉価商品を転売するために列をなす。
この対比は、中国という国家がどこに力を集中させ、誰を置き去りにしているかを如実に示している。
高品質と信頼の積み重ねによってしか生まれない「ブランド文化」は、数十年単位で蓄積される“遅い価値”だ。長年、“安く・早く・大量に”を信条としてきた中国経済は、その逆を行く時間軸への対応がまだ不十分だといえる。
”世界の工場”と呼ばれた中国にも陰りが見え始めている。
中国はもはや「発展途上国」ではない。だが、「成熟国」とも言いがたい。
通貨とは本来、自由と信頼の基に成り立つものだ。
だが中国の人民元は、透明性のある金融市場ではなく、政府による直接的な介入と統制によって“延命させられている”。
通貨が信用で支えられていない国は、“値がつく限りで機能する”だけであり、信用の失墜という現象は起きにくい――なぜなら、ハナから中国人民元は信用されていないからだ。
信用ゼロの通貨がこれ以上落ちようがない、既に織り込み済みというわけだ。
結果として、自由経済を名乗りながらも、国家主導のもとに為替支配によって支えられている経済となっており、自己矛盾の枠組みに落ち着き、通貨でさえも、その矛盾の中で生き延びる構造の一部となっている。
今の中国は、バブル後の日本の“縮みゆく経済”と、かつてのソ連が展開した”コメコン型勢力圏ゲーム”が融合した国家だと言えるかもしれない。
3.その二つが作る未来:成果を急ぐアメリカと、崩れずに耐える中国
アメリカと中国、両者ともに過去の歴史を繰り返し、拡張したような国家となっている。
・トランプ政権は、1期目で得られなかった”勝利”の再構築
→「成果が見える外交」「演出的で分かりやすい経済回復」を急いでいる。
・中国は、バブル崩壊後の疲労を抱えながらも、”延命すること”自体を戦略化
→海外投資、人民元の拡張、地の利、国内統制を通じた”長期持久戦”を展開しようとしている。
そのため、この二つの国家は交わることがなく、向かうのは戦争ではなく断絶になるだろう。
米中の分断は、なるべくしてなる
| アメリカの態度 | 中国の態度 |
|---|---|
| 関税・制裁・自国生産の強調 | 人民元・物流ルートの多極化 |
| ファーウェイ・TikTokなどの排除 | 国内デジタル産業の国家依存強化 |
| TSMC等の囲い込み | 技術自立化+AI・量子投資 |
| “味方か敵か”の踏み絵戦略 | “どっちつかず”を囲い込む戦略 |
→ 完全な経済デカップリング(分断)には至らないが、補完関係にも戻らない。
まるで冷え切った熟年夫婦の家庭内別居のように「接続したまま分断する」という“並列経済圏”に突入している。
世界は「貿易戦争2.0」から「覇権“共演”時代」へ
両国とも自国内に弱さを抱えており、その構図は―――
「覇権を取り戻したいアメリカ」vs「崩れることなく覇権を演出したい中国」
という形に収束していくだろう。
結果として起きるのは「勝負」でも「回避」でもなく「演出」。
例えば:
・2025年後半から2026年には、2020年ごろにあった米中間の”フェーズ1ディール的な経済合意”が再演されるかもしれない。
→アメリカ:「勝った」感の演出
→中国:「譲歩しないまま時間稼ぎが出来た」と評価
・台湾や南シナ海で、あえて”ギリギリのライン”を突きながらも全面衝突を避ける演出
それでも、このパフォーマンス的な冷戦は世界経済にとっては確実にコストになる。
物流は高騰し、技術は分散し、通貨はブロック化する。
国家は、「どちらの陣営か?」の選択を余儀なくされる。
4.まとめ
アメリカと中国は真向勝負しない。
前者はかつての栄光を取り戻すために焦り、後者は内部崩壊せず延命し存在することで勝ったように見せかける。
どちらもその裏には問題を抱えている。
どちらも過去の覇権のやり方をなぞりながら、それでも回り続けていく。
少しずつ今の”常識”や”栄光”を売ったり捨てたりしながら、新しい未来へと変貌していく。
今はまだ、世界は安定している。
欠落した現状という歪みの中から未来は生まれる。
その歪みがこの先どうなるのか分からない。
トランプの一手が、数手先を読んでいるとは思えない。
中国でさえ、どこで臨界点を迎えて崩壊するかも分からない。
だからこそ、今は何かを断言するよりも、この歪みの中で、何が動き、何が残るかを静かに見届けるほかないのかもしれない。

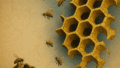
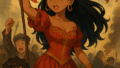
コメント