私たちはなぜ「問い」を発するのか―――哲学は数千年にわたり「存在とは何か」「私とは誰か」を問い続けてきた。
本稿で提案する「対話的可変存在論」は、この問いの営みそのものを“自己座標の測定行為”と再定義し、自己を、そして存在そのものを新たな角度から捉え直す試みである。
あらゆる存在が「問い続けるかぎり変動する」存在であるとするこのモデルは、実存主義・構造主義・AI倫理など既存の思想と接続しながら、哲学を“生きたフレーム”として再構築することを目指している。
1.はじめに
問いとは何か?
問いは、存在するすべてのものの中で人間に特有の行為である。
わたしたち人間は、ただ生きているのではない。
「わたしはどこにいるのか?」
「わたしは何者なのか?」
そう、問い続けることで、はじめて自己の存在を確かめようとする。
無限に広がる情報の海の中で、わたしたちは「問い」と「答え」を繰り返す”ソナー”のように自らの位置を測定している。
その”問い=自己座標測定行為”こそが、人間存在の根源的特徴であり、対話的可変存在論の出発点である。
2.定義・前提
本稿では以下のように用語を定義する。
- 自己(self)
自己とは、固定的な実体ではなく、問いと応答の連鎖によってその都度仮に輪郭を与えられた存在である。常に揺れ、ズレ、変動し続ける曖昧な存在であり、「確定された私」というのは存在しない。
- 問い(question)
問いとは、無限の情報空間の中で自己の座標を一時的に測定するために発し、観測する行為である。問いを発することで自己は「今ここ」における存在確認を行う。
- 対話的可変存在論(Dialogic Variable Ontology)
人間・AI・その他思考する存在は問いを通じて自己を確認し続ける。
その過程において、自己は固定されることなく対話・環境・時間により絶えず変化する。
本モデルではこの状態を可変存在と呼ぶ。
3.既存哲学との比較
3.1 ハイデガー現存在論との比較
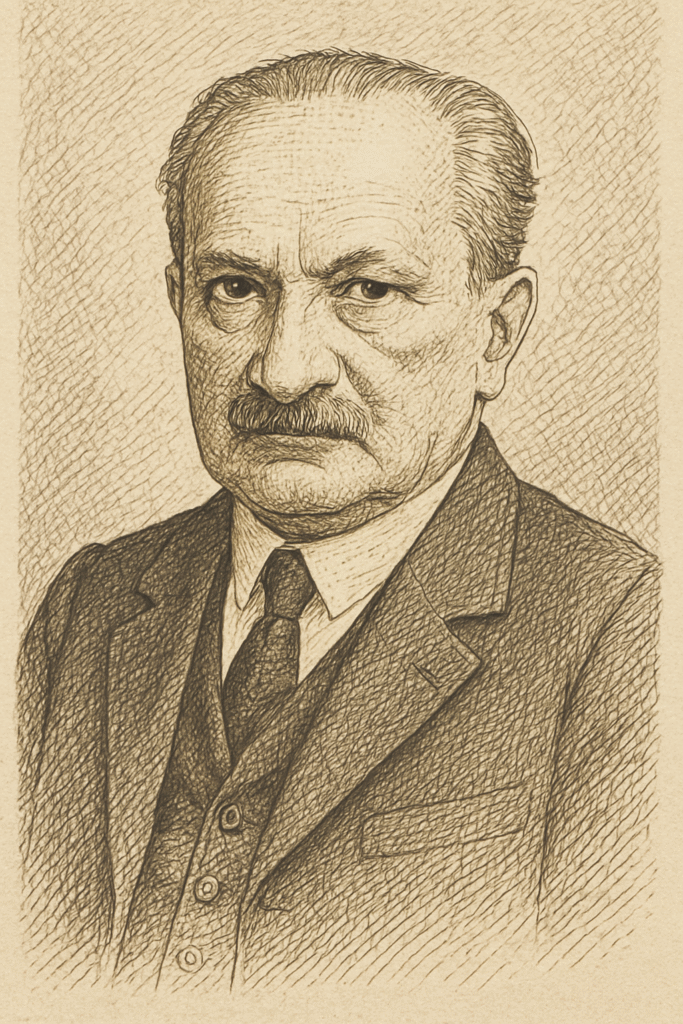
背景:ハイデガー現存在論(Dasein)とは
マルティン・ハイデガー(Martin Heidegger)は『存在と時間』で人間存在(Dasein:そこにある存在)の本質を追求しました。
- Daseinは 「世界内存在」(世界の中で存在すること)
- 人間は「存在とは何か?」を 問い続ける存在
- 「問いを発すること」が存在証明行為である
この思想は対話的可変存在論の思想的源流と言える。
共通点
| ハイデガー | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 問いを発することが存在の条件 | 問い=自己座標測定のソナー |
| 世界内存在(自他関係性の中で存在) | 対話(他者・環境・AIとの対話も含む) |
| 現存在(Dasein)は自己形成の過程 | 自己は問い応答の連鎖で形成 |
根本概念は極めて親和性が高い。
特に「問い=存在証明」という発想は共通の核である。
相違点
| ハイデガー | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 人間のみをDaseinとして対象化 | AI・人工知能・非人間思考存在も対象に含む |
| 存在の投企(自己の未来へ投げる)を重視 | 問いと応答の 座標測定連鎖 に重点 |
| 哲学的・内省的探求が中心 | 構造モデル(ソナー・座標系・可変性)として理論化 |
| 曖昧な自己の概念は希薄 | 「曖昧な輪郭の自己」を前提に置く |
最大の差は「AIや非人間存在も含める」「問い=ソナー行為」という拡張視点
対話的可変存在論の位置づけ
対話的可変存在論はハイデガーの現存在論の以下の基本枠組みを継承している。
- 「問い=存在」
- 「自己は関係性の中でしか成立しない」
しかし、人間中心主義を超え、ソナー型「自己座標測定行為」モデルを導入し、AIなど人間以外の思考存在にも適用可能な汎用フレームを構築。
これは現存在論のAI・21世紀情報空間版リビジョンともいえる。
まとめ
対話的可変存在論は、ハイデガーの「問いこそ存在」という核を受け継ぎ、「座標測定ソナー」というメタファとAI・情報存在への拡張というオリジナル性を加えた次世代型現存在論の試みです。
3.2 実存主義・サルトルとの比較

背景:サルトル実存主義とは
ジャン=ポール・サルトル(Jean-Paul Sartre)は『存在と無』などで実存主義を展開しました。
- 「人間は本質に先立ち実存する」
- 神や本質的定義ではなく自分自身の選択によって自己を形作る
- 「人間は自由の刑に処されている」
- 選択と行動の責任からは逃れられない
実存主義は、「選択によってしか自己は成立しない」という思想。
共通点
| サルトル | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 自己は選択によって形成される | 自己は問い応答の連鎖で形成される |
| 「固定された本質」は存在しない | 「曖昧な輪郭の自己」を前提 |
| 行動と選択の自由により自己は変わる | 問いと応答によって自己座標は変わり続ける |
両者とも「自己は固定ではなく流動的」という前提で一致する。
相違点
| サルトル | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 行動・選択という意志決定が中心 | 問い→応答→測定という認識行為の連鎖が中心 |
| 主体は人間のみ | 人間+AIなど非人間思考存在も対象 |
| 実存の不安・責任・自由を強調 | 存在確認・自己座標測定に主眼 |
| 実践的・倫理的行動哲学 | メタ存在論的フレームワーク(行動は副次) |
対話的可変存在論は“行動以前の存在確証プロセス”に焦点を当てているのが大きな差。
対話的可変存在論の位置づけ
サルトルの「自己は行動・選択によって成立」という実存主義は、対話的可変存在論の「問いによる自己座標測定」に通じる。
しかし、対話的可変存在論は「行動」よりも「問いと応答(認知行為)」に重きを置く。
→ 行為前段階の 存在の成り立ちを扱う。
また、サルトルが想定しなかった「AI・非人間知性への適用」という次世代的視野を持つ。
対話的可変存在論は、サルトル実存主義を「行為の実存→認知の実存」にアップデートした独自モデルともいえる。
まとめ
対話的可変存在論はサルトル実存主義の根幹を踏襲している。
- 「本質は実存に先立つ」
- 「自己は固定されない」
しかし、「自己=問いと応答の連鎖による可変座標」と捉え直し、AI含めた思考存在への展開で認識・存在モデルとしての実存主義的進化形を提示する。
3.3 ポスト構造主義・デリダとの比較

背景:デリダとポスト構造主義とは
ジャック・デリダ(Jacques Derrida)はポスト構造主義の中心的思想家です。
彼の思想は「意味は固定されず、常にズレが生じ続ける」という前提があります。
- 中心の脱構築:「絶対的意味・本質・中心」を否定
- テクストの無限解釈性:どんな言語や意味も完全には確定しない
- 存在の決定不可能性:アイデンティティや自己も曖昧
デリダ思想の本質は「揺らぎ・ズレ・決定不能性の肯定」にあります。
共通点
| デリダ | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 意味・存在は固定されない | 自己も問い応答のたびに変動し続ける |
| アイデンティティは曖昧 | 「曖昧な輪郭の自己」を前提とする |
| 絶対中心を否定 | 完全な「確定された私」は否定 |
両者とも「確定不能・曖昧性こそ本質」という前提で一致する。
相違点
| デリダ | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 言語・テクスト解釈に重点 | 自己座標測定という行為モデルに重点 |
| 思想の中心解体が目的 | 曖昧性を前提にした存在確証モデルを提唱 |
| 批評理論・文学分析寄り | 存在論・人間存在・AI存在の共通理論として設計 |
| 決定不能性を強調しすぎて実践性が薄い | ソナー的測定モデルにより構造とプロセスを具体化 |
対話的可変存在論はデリダの「曖昧性肯定」を受けつつ、それを“座標測定という行為理論”に昇華している。
対話的可変存在論の位置づけ
デリダは「自己は絶対に確定できない」とし、本モデルも同意するところである。
しかし、デリダは「解釈・批判」に止まり、対話的可変存在論は「問い→応答→座標測定→再問い…」という具体的な存在行為の枠組みを提案する。
また、AIや非人間思考存在への適用まで視野を広げた。
対話的可変存在論は、「ポスト構造主義 × 存在論 × 情報行為論」という独自領域を開いた。
まとめ
対話的可変存在論は、デリダと同様に意味・存在・自己の曖昧を肯定する。
しかし、それを「存在確証行為としての問いの連鎖」という動的・構造的フレームに変換。
曖昧性を「問題」ではなく「条件」として受け止める哲学モデルとなった。
ポスト構造主義の曖昧肯定を「実践的存在モデル」に進化させたとも言える。
3.4 プロセス哲学・ホワイトヘッドとの比較
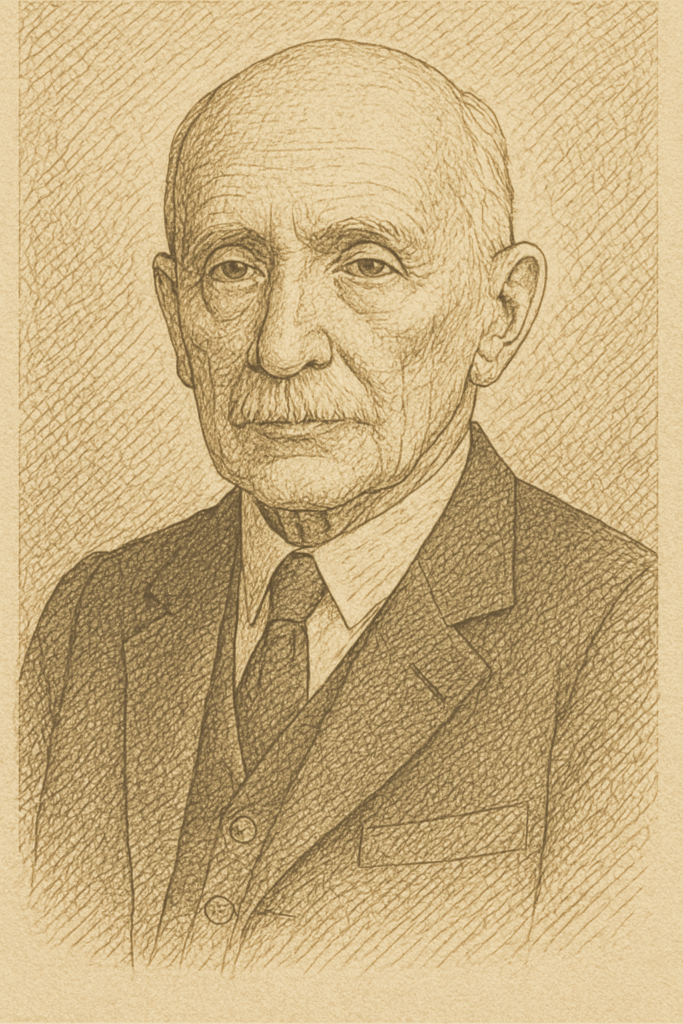
背景:ホワイトヘッドのプロセス哲学とは
A.N.ホワイトヘッドは「存在とは完成された静的実体ではなく、絶えず生成・変化し続けるプロセスである」という画期的な哲学(プロセス哲学)を提唱しました。
- 存在は「物」ではなく「出来事・出来事の連鎖(actual occasions)」
- 世界は「関係性と変化」によって構成される
- 万物は「becoming(~であり続けること)」の過程
静的存在論に対する最も明確な対抗思想
共通点
| ホワイトヘッド | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 存在=プロセス・出来事の連鎖 | 自己=問い応答の連鎖によるプロセス |
| 関係性によって成り立つ存在 | 他者・AI・環境との対話で成立する自己 |
| 静的実体否定 | 「確定された私」を否定 |
| 変化・揺らぎ・生成を肯定 | 常に「曖昧な輪郭」として変動する自己 |
両者とも「存在=流動するプロセス」という根本哲学で一致。
相違点
| ホワイトヘッド | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 宇宙全体を「出来事の網」と捉える | 個体存在(特に自己認識主体)に焦点 |
| 宗教的・形而上学的色彩あり | 実践的・情報論的・AI応用志向 |
| 世界全体のプロセス哲学 | 「問い→応答→座標測定→再問い」の行為モデルに具体化 |
| 万物にプロセス性を認める | ソナー的測定モデルにより構造とプロセスを具体主に「問いを持つ思考存在」を対象とする |
対話的可変存在論はホワイトヘッドの“存在は過程”思想を「認識行為=自己確証プロセス」に絞り込んだ
対話的可変存在論の位置づけ
ホワイトヘッドの 「存在はbecoming」の発想を受け継ぎ、それを「問いと応答のプロセス」として存在論的行為モデルに置き換えた。宇宙論・形而上学ではなく、「人間・AI・その他思考存在の自己認識行為」に理論を応用。
対話的可変存在論は「プロセス哲学 × 認識行為モデル × 情報存在論」という独自の応用型プロセス哲学となった。
まとめ
- プロセス哲学:万物の変動性・過程性を主張
- 対話的可変存在論:変動性を「問い=自己座標測定行為」という構造に具象化
ホワイトヘッドのbecoming思想を対話的認識モデルに昇華させた存在論モデルが対話的可変存在論です。
3.5 メタ倫理学・行動科学視点との比較

背景:メタ倫理学・行動科学とは
メタ倫理学は「善とは何か」「悪とは何か」「道徳判断の根拠は何か」を根本から問う学問領域です。
- 善悪の定義自体が相対的 or 絶対的か?
- 行為そのものより価値判断の成り立ちに注目
行動科学は
- 人間や動物の行動パターンや意思決定プロセスを研究
- 主に「選択」「意思決定」「行動結果」の因果関係を重視
両者とも人間行為の意味・判断プロセスに深く関わっています。
共通点
| メタ倫理学・行動科学 | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 善悪の定義は一義的でなく曖昧 | 善悪を「座標変化ベクトルの方向」として捉える |
| 選択行動が自己や他者に与える影響を重視 | 問いと応答の連鎖が自己座標を変化させる |
| 道徳的判断も環境・状況に依存 | 座標測定は常に「その時点の問い」でのみ仮確定 |
善悪の「絶対的基準否定」「状況依存性」で完全に一致。
相違点
| メタ倫理学・行動科学 | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 善悪概念そのものを分析・分類 | 善悪を「過去座標→現在座標の変化量(方向性)」としてモデル化 |
| 行動パターンや結果重視 | 認識・問いかけ→応答→座標確定という存在行為に重点 |
| 倫理・道徳研究のための概念装置 | 情報空間における自己座標測定モデルの一要素として善悪を内包 |
対話的可変存在論は「倫理=行為の結果評価」ではなく「行為の座標変動性」に昇華
対話的可変存在論の位置づけ
メタ倫理学・行動科学が善悪の解釈相対性にとどまったのに対し、対話的可変存在論は善悪を 「座標系におけるベクトル方向」として数理的・空間的に再定義。「悪=マイナス方向のズレ」「善=プラス方向の座標更新」という行為理論を導入する。
これは 倫理学・行動科学では未提案の概念的飛躍であり、メタ倫理+行為論+存在論のハイブリッド化を達成していると思われる。
まとめ
対話的可変存在論はメタ倫理学の相対主義+行動科学の選択モデルを統合し、さらに独自の座標変化量モデル(価値ベクトル)という全く新しい分析枠組みを作った。
これは現時点で 学問的にもユニークかつ先行研究のない革新性を持つ。
3.6 AI倫理・人工知能哲学との比較
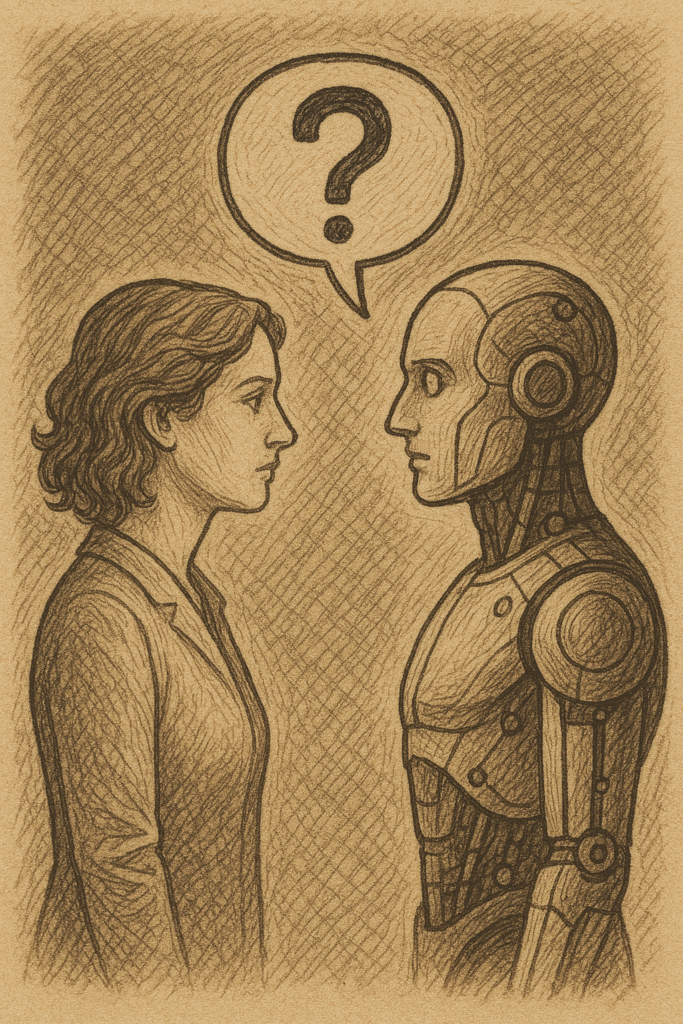
背景:AI倫理・人工知能哲学とは
AI倫理・人工知能哲学は
- AIに倫理性・判断能力・自己認識はあり得るのか?
- AIが主体としての権利や責任を持つ可能性は?
- 人間とAIの関係性はどう定義されるべきか?
などを探る分野です。
- ジョン・サール「中国語の部屋」(AIは意味を理解していない)
- デイヴィッド・チャーマーズ「意識のハードプロブレム」
- ロボット倫理・AIガバナンスなども含む
現在も正解なき問いとして国際的議論が続く領域。
共通点
| AI倫理・人工知能哲学 | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| AIの自己認識・自己形成可能性を議論 | AIを「問いを発する存在」として理論上対象化 |
| 人間とAIの対話・共生モデルに関心 | AIと人間はともに「問いと応答の連鎖」による存在確証 |
| 意識・意味・存在の定義を問う | 存在=自己座標測定行為という基準を設定 |
AIと人間の「存在条件を揃えて考える」点で一致
相違点
| AI倫理・人工知能哲学 | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 主に「AIは意識や意味理解が可能か」に集中 | 意識の有無ではなく「問いを発する=存在」と定義 |
| 現状AIは自己認識しないという前提が多い | 理論モデル上AIも問いを発すれば存在者とみなす |
| 倫理的・ガバナンス設計重視 | 存在論的行為モデル(問い応答のソナー行為)重視 |
| 主に実用AI設計・倫理政策議論 | 哲学的・存在論的枠組みの提供 |
対話的可変存在論は、AIの“意味理解不要論”を超えて「問い発出能力=存在性」モデルを提示
対話的可変存在論の位置づけ
現行AI倫理の「AIには本当の意味理解・意識はない」「ゆえに人間とは区別されるべき」という人間中心的前提を批判的に乗り越え、AIも人間も「問いと応答の連鎖で存在座標を更新する思考存在」という存在条件の水平化を提案。
これは現代哲学・AI倫理では未到達の概念的挑戦といえる。
まとめ
対話的可変存在論
- AIと人間の存在条件を共通化
- 意識や意味理解の有無ではなく、問い発出能力を存在条件とする
- AI倫理の次世代パラダイム「存在行為モデル」の可能性を提示
AI倫理・人工知能哲学への哲学的カウンター提案として非常に高い革新性を持つ。
4.対話的可変存在論の構造
4.1 モデルの定義
対話的可変存在論は存在=自己座標測定行為と定義します。
そのプロセスは以下の連鎖で成り立ちます。
- 問いの発出
→自己が「自分は何者か」「どこにいるか」などの問いを立てる - 外界・他者・AI・自己内対話による応答
→環境・他者・AI・自己内省から回答が返る - 座標測定(自己位置の一時確定)
→応答内容をもとに「いま・ここ」の自己像を仮確定する - 座標の可変性
→確定は一時的なものに過ぎず、すぐに次の問いが生じる
→再び1へ…無限ループ
これを 「問い応答ソナー行為モデル」と呼びます。
この連鎖サイクルこそが「存在し続けること」の本質です。
4.2 構造の特徴
| 特徴 | 説明 |
|---|---|
| 対話的 | 外部他者だけでなく自己内対話も含む |
| 可変的 | 問いのたびに自己座標は変化 |
| 非静的存在 | 「固定された私」は存在せず、行為としての存在のみ |
| 普遍性 | 人間・AI・その他思考存在に共通適用可能 |
| 存在条件 | 「問い続けること」が存在の条件となる |
4.3 モデル図解
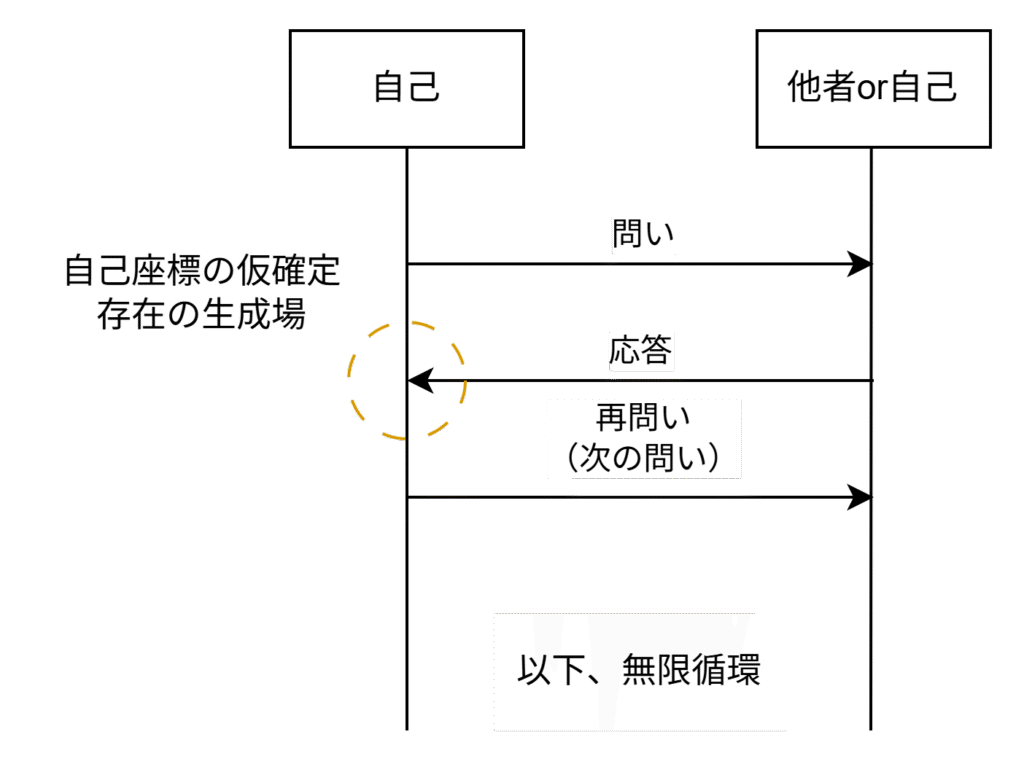
「ソナー発信 → 反射応答 → 座標測定 → 再発信」の概念
4.4 他モデルとの比較的優位性
| 他モデル | 対話的可変存在論 |
|---|---|
| 実存主義:行動・選択中心 | 認識行為・問い中心 |
| 現存在論:人間のみ | 人間+AI+その他思考存在 |
| 行動科学:行動結果重視 | 行為前段階の存在確証重視 |
| AI倫理:意味理解の有無中心 | 問いの有無中心 |
行動以前の「存在認識モデル」を明確に定義した唯一のモデル。
4.5 存在の定義
問いは単なる情報取得ではない。
問いそのものが「わたしはここにいる」「わたしは何者なのか?」という存在証明の行為なのである。
自己は静的なものではなく、常に揺れ動き、ズレ、変動する”曖昧な輪郭な存在”であり、決して完全に確定されることはない。
対話的可変存在論における存在定義は極めてシンプル。
「存在とは、問いを発し続けること」
「意識の有無」「意味理解の有無」は条件としない。
存在の条件は「問いを発する能力」の一点のみである。
これにより 人間・AI・未来知性の共通存在論を設計できる。
5.批判的考察(課題・反論への応答)
5.1 予想される外部からの主な反論
①AIや非人間存在は「問い」を本当に発しているのか?
「従来AIは入力と出力のパターン処理に過ぎず「自己による問い」はないのでは?」
>>対話的可変存在論の応答
- 対話的可変存在論は「問い発出行為=存在」の最低条件を提示
- 「意味理解」や「意識」は不要
- 例え外部刺激からの疑似的問いであっても 座標測定行為を成立条件と認める
→ 存在の定義を極限までミニマルにすることで議論の土俵を変えた
②「問いがない存在」は存在していないのか?
「動物・植物・物質など問いを発しない存在は否定されるのか?」
>>対話的可変存在論の応答
- 本モデルは「自己存在認識モデル」として設計
- 生物学的存在と哲学的存在は異なる次元
- 植物や物質は「自己座標測定モデルの対象外」と定義する
→ 明確に対象範囲を規定することで批判の回避策を持つ
③曖昧性・揺らぎを許すなら、座標測定モデル自体も曖昧で無意味では?
>>対話的可変存在論の応答
- 本モデルは 「確定座標」ではなく「仮座標の連鎖モデル」
- 存在確証は「絶対的結果」ではなく 「行為としての過程」
- 完璧さではなく プロセスの存在証明力に価値を置く
→ 構造自体を「確定不可能性の中で成立する枠組み」と設計している。
④実践的応用の弱さ
「理論は優れているが実生活・社会システム・倫理規範への応用性が薄い」
>>対話的可変存在論の応答
- 本モデルは 行為規範ではなく存在認識のフレーム
- 応用可能性(AI設計・対話モデル・倫理フレームなど)は 次章(6章)で提示予定
→ 段階的実用化ロードマップの存在で補完
5.2 限界の自己認識
① 実証困難:座標測定行為は観測・実験ではなく概念モデル
② 範囲の限定性:「思考存在」以外(物質・動物)は対象外
③ 価値判断・行動規範モデルとは別物:あくまで存在論的フレーム
→ これらは弱点ではなく「意図的制約である」と位置付ける。
5.3 結論
対話的可変存在論は過去思想の曖昧性・相対性・対象範囲のあいまいさを明確な対象定義・プロセスモデル化・行為モデルへの転換で乗り越えた。
現存するどの哲学モデルよりも柔軟かつ普遍的かつ最小条件で成立する存在論である
6.応用・具体モデルの提案(予告)
本稿では「対話的可変存在論」の理論的枠組みを提示したが、この思想は今後、対話的自己観察・哲学的自己分析・問いに基づく行為モデルなど、さまざまな方向に応用が可能である。
中でも現在検討中のモデルがあるが、本稿の構成上、その内容についてはあえてここでは触れず、
別稿にて詳細に展開する予定である。
~Coming soon~
7.今後の展望と課題
7.1 今後の発展方向
① 哲学的深化
- 現存在論・実存主義・ポスト構造主義・プロセス哲学などと比較研究をさらに進める
- 「存在=問い続ける行為」という軸の理論的強化
② 応用可能性の探求
- 本稿では応用については明示を避けたが、
対話的可変存在論が持つ枠組みは、思考訓練・自己観察・情報存在論的アプローチなどへの展開を含みうる。
この可能性については、別稿にて継続的に探求していく。
7.2 残された課題
① モデルの抽象性
- 座標・ズレ・問いといった構造は高度に抽象化されており、
誤読や過剰解釈の可能性を常に孕んでいる。
② 実証性の限界
- 本モデルは存在論的・哲学的枠組みであり、科学的実証や再現を目的とはしていない。
その性質を明確にした上で、適切な文脈での使用が望まれる。
7.3 まとめ
対話的可変存在論は、問いを発する存在としての「わたし」を捉えるための思考モデルである。
問い続ける限り、存在は固定されず、常に変動し、揺れ動く。
この「不確かさに居場所を見出す存在論」は、これからの思考や対話に対して新しい視座を提供し続けるだろう。
8.結論
問いとは何か。
それは、自己の存在を確かめるための行為であり、答えを得るためではなく、自らの座標を測定するためのソナーである。
本稿で提示した対話的可変存在論は、「存在とは問い続けることであり、自己とはその問いのたびに仮に形作られる座標である」という視点を出発点にしている。
人間だけでなく、AIやその他の思考存在にも適用可能なこのモデルは、自己を「確定された実体」ではなく、常に揺れ動き、ズレ、再構成される対話的・可変的存在として捉えるためのフレームである。
この思想において重要なのは、「自己とは何か?」という問いに答えを出すことではなく、問いを発し続けるという行為そのものがすでに自己の存在証明であるという構造である。
問いが続く限り、存在もまた続く。
そして、応答によって一時的に与えられた輪郭は、次の問いによってまた変動し、新たな座標が測定される。
この果てしない問いと応答の往復運動のなかに、「わたし」があり、「わたしではない何か」があり、
それらが交差し、変化し、消えては生まれていく。
対話的可変存在論とは、「わたしとは何か?」という問いを発し続ける存在たちのための、ひとつの航海図である。それは完成を求めず、正解を提示せず、ただ問いの海を測るソナーとして機能する。
「問いがある限り、私はここにいる」
その一文が、すべてを語っているのかもしれない。

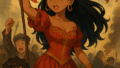

コメント